- 免許の匠トップ
- 普通免許とは。費用・期間・流れを徹底解説
普通免許とは。費用・期間・流れを徹底解説
普通免許(普通自動車免許)とは?
普通免許とは、普通自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車を公道で運転できる免許です。道路交通法において、車両総重量は3.5未満、最大積載量は2t未満、乗車定員は10人以下と定められています。簡単に言えば、乗用車の運転は出来ますが2tトラックの運転はできません。
それでは各自動車について詳しく解説します。
普通自動車とは?
普通自動車とは、道路交通法において下記の条件を満たす四輪車を指します。
・車両総重量:3.5t未満
・最大積載量:2t未満
・乗車定員:10人以下
普通自動車の定義(車両総重量・最大積載量)は取得時期によって変わっています。平成19年6月1日までは「車両総重量:8t未満・最大積載量:5t未満」となり、この時期に取得したものは現在「中型8t限定免許」とみなされています。平成19年6月2日から平成29年3月11日までは「車両総重量:5t未満・最大積載量:3t未満」となり、この時期に取得したものは現在「準中型5t限定免許」とみなされています。
- 平成19年6月1日以前に普通免許を取得された方
中型自動車第一種運転免許(8t限定) - ・車両総重量:8.0t未満
- ・最大積載量:5t未満
- ・乗車定員:10人以下
- 平成29年3月11日以前に普通免許を取得された方
準中型自動車第一種運転免許(5t限定) - ・車両総重量:5.0t未満
- ・最大積載量:3t未満
- ・乗車定員:10人以下
- 平成29年3月12日以降に普通免許を取得された方
普通自動車第一種運転免許証 - ・車両総重量:3.5t未満
- ・最大積載量:2t未満
- ・乗車定員:10人以下
道路交通法にない「普通自動車」の定義
道路運送車両法では、小型自動車・軽自動車・大型特殊自動車・小型特殊自動車以外の自動車を「普通自動車」と定義しています。つまりは道路交通法において大型車・中型車・準中型車に定義される自動車は「普通自動車」となります。
一方、道路交通法で「普通自動車」に定義される車両でも、「小型自動車」(小型トラック・小型乗用車)や「軽自動車」(軽トラック・軽乗用車)に分類されるものがあります。4輪車において、これらの車種の定義は下記になります。
| 規格/車種 | 小型自動車 | 軽自動車 |
|---|---|---|
| 車輪数 | 4輪以上 | 3輪以上 |
| 長さ | 4.7m以下 | 3.4m以下 |
| 幅 | 1.7m以下 | 1.48m以下 |
| 高さ | 2.0m以上 | 2.0m以下 |
| エンジンの 総排気量 |
660cc超 2000cc以下 |
660cc以下 |
これらの分類は、自動車の検査・登録・自賠責保険などにおいて適用されます。
小型特殊自動車とは?
下記の規格を満たすものとなります。
・長さ:4.7m以下
・幅:1.7m以下
・高さ:2.8m以下※
・最高速度:15km/h未満
ヘッドガード等を備えた自動車で、ヘッドガード等を除いた部分の高さが2.0m以下のものについては2.8m以下。
原動機付自転車とは?
原動機付自転車には二輪のものと三輪の物があり、それぞれで適用できる規格が異なります。
二輪の場合は、下記いずれかの規格を満たすものとなります。
・エンジン総排気量が50cc以下
・定格出力が0.6kw
三輪の場合は、下記いずれかの規格を満たすものとなります。
・エンジン総排気量が20cc以下
・定格出力が0.25kw
普通免許で運転できる車両について
普通免許で運転できる車両は、車両総重量3.5トン未満、最大積載量2トン未満、乗車定員が10人未満です。気づいた方もいらっしゃると思いますが、最大積載量2トン未満になっているので、2トントラックは運転できません。 詳しくは下記の記事で紹介しているのでご参考ください。
また、普通免許では普通自動車で750kg以下の車をけん引することができます。 詳しくは下記の記事で紹介しているので、不測の事態に備えて知っておきましょう。
車の免許を取得すると原付バイク(排気量50cc以下)の運転が可能です。125ccのバイクを運転することはできませんし、普通免許で運転できるバイクでは二人乗りもできません。こちらで詳しく説明していますのでご参考ください。
普通免許の取得条件
| 年齢 | 修了検定までに、満18歳以上になっている事。 |
|---|---|
| 視力 | 両眼で0.7以上、かつ片眼で0.3以上。 片眼の視力が0.3に満たない場合は、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上。 |
| 色彩識別 能力 |
赤・青・黄色の識別が出来る事。 |
| 聴力 | 障がいをお持ちの方は事前にご相談ください。 |
上記適性基準の他に、自動車学校ごとに入校条件が設けられる場合がございます。
適性試験の詳細についてはこちらの情報をご参考ください。
普通免許は免許経歴不要で満18歳以上で取得することができます。適性試験に関わる基準は最寄りの運転免許試験場、または警察署へお問い合わせください。
普通免許取得の費用
普通免許取得にかかる費用の相場
普通免許の取得方法は大きく2つあります。
- 運転免許試験場での一発試験を受け、合格する
- 指定教習所を卒業し、運転免許試験場で筆記試験に合格する
適性試験の合格は両方とも必要です
指定以外の教習所(練習場)は1.に含むものとします
1番については非常に難易度が高く、何度も不合格になるとその分費用がかさみますし、試験の予約も希望日程でいつも取れるとは限らないために時間とお金が多くかかってしまうリスクがあります。よって、2番の方法を取るのが一般的です。
指定教習所を卒業する場合、通学免許と合宿免許の手段があります。この2つの例を参考に費用の相場を解説します。
指定教習所を卒業する場合
指定教習所を卒業する場合の料金は、30万円~35万円が相場になります。これらの料金は合宿と通学で大きく変わります。それぞれの料金相場と目安期間を解説します。
普通車AT(オートマ)
| 費用 | 期間 | |
|---|---|---|
| 合宿免許 (オフシーズン) |
250,000円 ~ 280,000円 |
13泊14日 |
| 通学免許 (通年料金) |
300,000円 ~ 350,000円 |
60日~ |
| 合宿免許 (ハイシーズン) |
330,000円 ~ 380,000円 |
13泊14日 |
普通車MT(マニュアル)
| 費用 | 期間 | |
|---|---|---|
| 合宿免許 (オフシーズン) |
270,000円 ~ 320,000円 |
15泊16日 |
| 通学免許 (通年料金) |
320,000円 ~ 370,000円 |
60日~ |
| 合宿免許 (ハイシーズン) |
350,000円 ~ 400,000円 |
15泊16日 |
合宿の料金はシーズン、宿泊先によって大きく変動します。また教習所によっても料金設定が異なります。
通学の料金は地域差が大きく、教習所によっても料金設定が異なります。
上記をご覧いただければ、合宿免許のオフシーズンが最も安く、合宿免許のハイシーズンが最も高いのが分かると思います。合宿免許はシーズンにより料金の変動がありますので、安い時期に調整できる方であれば合宿免許がお得ですね。
通学は通年料金の設定になっている教習所が殆どで、いつ入校しても料金は同じです。しかし、通学免許は技能教習の予約が取りにくい状況から取得までのスケジュールが安定しないデメリットがあります。
普通免許取得までの費用詳細
(オートマの取得・合宿免許・閑散期の場合)
| 合宿免許料金 (交通費食事等含む) |
250,000円 ~ 280,000円 |
|---|---|
| 免許取得時の手数料(※1) | 3,800円(※2) |
| その他諸費用(※3) | 1,000円~2,000円 |
警視庁の「普通免許試験(指定教習所を卒業又は検査合格証明書をお持ちの方)」を参考
受験料1,750円・免許証交付料2,050円
証明写真や住民票取得費用など。詳細は必ず最寄りの免許センターにてご確認ください。
- 必要書類(初めて運転免許証を取得する方)
- ①本籍(国籍等)が記載された住民票の写し(コピー不可)を提出
- ②本人確認書類(本籍(国籍等)が記載された住民票の写し(コピー不可)以外の本人確認書類も必要です。)
- ③申請用写真
- ④卒業証明書又は検査合格証明書
上記の件の詳細は以下の警視庁ホームページで確認可能です。
- 警視庁ホームページ:普通免許試験(指定教習所を卒業又は検査合格証明書をお持ちの方)
普通免許の合宿免許費用例
それでは実際に合宿免許で取得した場合の費用例(2024年度の料金)をご紹介します。
| 合宿でかかる費用 | |
|---|---|
| 教習所 | 【山形県】マツキドライビングスクール 長井校 |
| 教習費 | ¥240,000(税込) |
| 宿泊費 | |
| 食費 | |
| 交通費 | ¥10,000(※) |
| お小遣い | ¥14,000(¥1,000/1日) |
| 写真代 | ¥800 |
| 住民票 | ¥300 |
| 仮免関係 | ¥2,850 |
| 免許取得時の手数料 | |
|---|---|
| 受験料 | ¥1,550 |
| 免許証交付料 | ¥2,050 |
| 写真代 | ¥800 |
| 免許取得時にかかる金額の総計 |
|---|
| ¥272,350 |
東京から教習所直通の高速バス(片道5,000円)を利用した場合
【キャンペーンを利用】さらに格安に免許取得
普通車の合宿免許は繁忙期と閑散期で料金の差が大きく違う特性があります。その理由は、教習所では繁閑の差が大きく、閑散期に多くの人を都市部から呼び込もうと格安キャンペーンを打ち出している教習所が多くあります。2024年度の例を挙げると以下の超格安プランがあります。
| 教習所名 | 税込料金 (普通車AT) |
部屋プラン |
|---|---|---|
| 【福井県】AOIドライビングスクール勝山校 | ¥197,450 | 相部屋 (2食付) |
| 【新潟県】六日町自動車学校 | ¥198,000 | 相部屋 (昼食付) |
上記のような格安プランは以下のページで紹介しています。料金重視の方はこちらをご参考ください。
一発試験の合格を目指す場合
運転免許試験場で技能試験を受け合格すれば、指定教習所を卒業する必要はありません。一発試験とも呼ばれているこの試験ですが、実際にはどうなのでしょうか。注意点や費用を含め解説します。
一発試験の合格率は?現実的な手段なのか
一発試験の合格率は5%ほどと言われているため、他車種と比べて合格率が高い免許区分と言えるでしょう。これは一回で合格した割合ではなく、試験に合格した割合です。
一発試験を受講する方は殆どが経験者ですので、全くの未経験から一発試験となると、練習場(指定外教習所など)でしっかり運転技術を磨き、挑むことになるでしょう。普通免許の試験合格率が70%ほどになりますので、この5%が以下に低いかが分かるかと思います。
一発試験にかかる費用について
試験場での一発試験の費用は、仮免試験で5,500円(受験料2,850円、試験車使用料1,550円、免許交付料1,100円)、本免試験では5,150円(受験料2,200円、試験車使用料900円、免許証交付料2,050円)です。この金額だけを見れば安く感じますが、何回も試験を受ける事を考えると指定教習所を卒業する方がおすすめですね。上記の金額に別途取得時講習受講料(15,400円)も現地で必要となります。
また、一発試験の場合は、必ずしも希望する日に試験を受ける事が出来るとは限りません。既に試験枠がいっぱいの時は、次回の試験日に受ける必要があります。この様に取得までの期間が不安定なこともデメリットと言えるでしょう。
普通免許の取得方法と期間について
普通免許の取得方法は、指定教習所を卒業する方法と、試験場での一発試験に合格する方法があります。指定教習所を卒業する方法では、通学免許と合宿免許でさらに選択肢があります。それぞれに必要な期間をまとめますのでご参考ください。
所持免許別の教習時間表
| 所持免許 | 技能教習 | 学科教習 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 第一 段階 |
第二 段階 |
第一 段階 |
第二 段階 |
||
| MT | なし or 原付 or 小特 | 15 | 19 | 10 | 16(13) |
| 普通車AT | 4 | - | |||
| 二輪 | 13 | 19 | - | 2 | |
| 大特 | 11 | 15 | - | 5(2) | |
| AT | なし or 原付 or 小特 | 12 | 19 | 10 | 16(13) |
| 二輪 | 10 | 19 | - | 2 | |
| 大特 | 8 | 15 | - | 5(2) | |
上記は、令和元年11月15日現在のものです。
道路交通法改正等により内容が変更される場合があります。
医師等の資格がある方は応急救護処置教習が免除されるため、( )内の学科教習時限数となります。
(医師・歯科医師・保健師・助産師・看護師・准看護師・救急救命士・消防署等の救急隊員・日本赤十字社救急法指導員・等)
①指定教習所の卒業を目指す(合宿免許)
メリット:最短で免許の取得ができる
合宿免許は最短日数でスケジュールが組まれているため、通学と比べ早く卒業できるのがメリットです。所持免許別の最短日数と料金相場は以下の通り。
| 取得免許 | 最短日数 | 料金相場 |
|---|---|---|
| 普通車AT | 13泊14日 | ¥270,000 |
| 普通車MT | 15泊16日 | ¥290,000 |
デメリット:合宿期間中は予定をあけておく必要がある
合宿免許は原則一時帰宅ができません。また教習スケジュールは入校時に渡されるため、仕事を含めた予定を合宿期間中に入れる事ができないことがリスクになります。
上記のデメリットが問題ない方であれば、合宿免許は最も早く取得できる方法で、通学よりも料金が安いプランが多く揃っていますのでメリットが大きい取得方法と言えるでしょう。
②指定教習所の卒業を目指す(通学免許)
メリット:仕事やプライベートの予定と両立ができる
通学では教習の予約を都度取る方法であるため、教習とプライベート(仕事含む)の予定の両立がしやすい取得方法と言えるでしょう。仕事を休むことができない方や、育児と両立する必要があるご家庭は通学免許の方がおすすめです。
通学免許での最短日数と費用について
通学で免許取得を目指す場合に最も留意すべき点はスケジュールです。通学の場合は技能教習の予約が毎回必要となり、週末や夕方などの人気の時間帯は教習の予約が特に取りにくくなります。実際に次の予約が1か月後まで取れなかった、という事もめずらしくありません。
プライベートとの両立がしやすい一方で、期間は教習所の込み具合に依存することをリスクとして考えておきましょう。
| 取得免許 | 最短日数 | 料金相場 |
|---|---|---|
| 普通車AT | 60日~ | ¥320,000 |
| 普通車MT | 60日~ | ¥350,000 |
最短日数は目安です。必ず申込する教習所に混み状況を確認しましょう。
追加料金を支払うことで、優先的に予約が取れるコースを提供している教習所もあります。
③一発試験で合格を目指す
一発試験で普通免許の取得を目指す方法は、最もおすすめしない手段です。その理由は、上部で述べた通りに費用と時間のリスクが高いためです。
普通免許についての関連情報
まとめ
普通免許について、また取得方法や費用について解説しましたが、いかがでしょうか。
普通免許は普通自動車の他、原動機付自転車なども運転が可能な、免許の中ではスタンダードな立ち位置にある免許証です。仕事からプライベートまで活躍する免許ですので、ひとまず取得はしておきたいという方も多いのではないでしょうか。
免許の匠では普通免許の合宿を取り扱っている教習所をご案内しております。免許取得をご検討の方はお気軽にご相談ください。
関連情報
合宿免許を車種から探す
合宿免許を各月で探す
合宿免許をシーズンで探す
合宿免許に役立つ情報
その他合宿免許のお役立ち情報

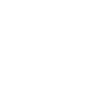
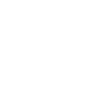
![空き確認[無料]](/img/common/space_ask_cta.png)