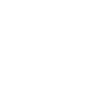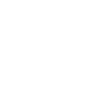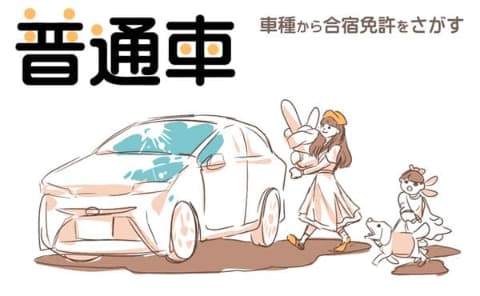- 免許の匠トップ
- 免許取消処分(行政処分)を受けた方の再取得
免許取消処分(行政処分)を受けた方の再取得
交通違反による運転免許の取消処分(行政処分)を受けた方が免許再取得を目指すための方法を解説します。取消処分になった経緯で取得までの段取りが異なります。個々のケースに合わせてご参考ください。
10月~12月の合宿免許おすすめプラン
運転免許の取消処分とは?
運転免許の取消処分とは、交通違反などで免許の効力が取り消されてしまう最も重い処分です。免許を持っていない状態になりますので、車両の運転はもちろんできません。取消処分を受けた後に車両を運転すると無免許運転となりますので注意しましょう。
行政処分は交通違反の内容により点数計算を行い、処分内容が決まります。処分基準点数は少し複雑ですので警視庁のホームページの内容を参考に分かりやすく解説します。
点数制度について
行政処分の内容が決まる点数について
どの様な行政処分になるかは点数計算により決定されます。初めての行政処分と過去に行政処分歴が場合では計算方法が変わります。
例えば行政処分歴が無く点数が3点の場合は処分はありませんが、過去に2回行政処分歴がある場合は120日の免許停止となります。
具体的な点数はこちらを参考にしてください。
行政処分・刑事処分・民事処分
行政処分
行政処分とは公安委員会が行う処分のことであり、前科は特につきません。しかし反則金を支払わないなど処分内容に従わない場合等、刑事処分になる可能性もありますので注意しましょう。
刑事処分
刑事処分とは過去の行為に対して制裁が行われる処分となり、行政処分とは本質的に異なります。主に重大な交通違反に対して行われるものであり、裁判所で処理され、前科がつきます。
例えば酒酔い運転の場合、5年以下の懲役又は100万円以下の刑事処分に該当し、検知拒否も3年以下の懲役又は50万円以下の罰金と重たい処罰が定められています。
民事処分
上記の他には民事処分があります。民事処分とは、交通事故を起こしてしまった際の加害者への損害賠償です。
車両の修理代、病院での治療費、後遺症が残る場合はその保障が該当します。
意見の聴取・聴聞制度
処分が最終判断される前に自身に有利になる意見を提出することが出来る制度です。
これは90日以上の停止や取消処分など、重い処分に適用され、意見の聴取及び聴聞の開催日は予め通知されます。
もちろん出席しなくても構いませんが、処分が軽減される例もあるので伝えたい事がある場合は出席すると良いでしょう。
行政処分の執行
意見聴取が終わり処分内容が決定されると正式に処分が執行されます。
処分が執行されてからは車両を運転できないのはもちろんのこと、欠格期間中は運転免許の再取得も出来ません。
運転免許を再取得する流れ
免許の取消処分を受けてしまった場合、免許の再取得はどの様な流れになるのかを解説します。
![空き確認[無料]](/img/common/space_ask_cta.png)
欠格期間とは
欠格期間とは、運転免許を取得できない期間を指します。免許証を取得できませんから、もちろん自動車を運転することもできません。欠格期間は前歴や違反点数、そしてどんな違反(一般違反行為、または特定違反行為)をして行政処分になったかにより異なり、最長で10年にもなります。
特定違反行為とは悪質・危険な違反行為で、それ以外の違反を一般違反行為とされています。
特定行為の具体的な例は、運転致死行為や飲酒運転、ひき逃げ等が該当します。
欠格期間は通知書で確認することができます。また、通知書を紛失したとしても警察署に問合せが可能です。欠格期間が満了しない限り、運転免許の再取得ができません。欠格期間の満了日を忘れないようにしましょう。
取消処分者講習とは
運転免許の取消処分を受けた方は、免許の再取得の前に必ず取消処分者講習を受講する必要があります。取消処分者講習は以下の2つに分類されます。
・一般講習
・飲酒講習
一般講習は飲酒や酒気帯び以外での行政処分を受けた方が対象となります。飲酒講習はその名の通り、飲酒運転に関わる違反で行政処分を受けた方向けの講習です。講習は全て予約制となります。一般講習は2日間連続で行いますが、飲酒講習は初回講習を受けから日にちを明け2回目を受講します。
運転免許再取得時の注意
取消処分を受けてから運転免許の再取得をする場合、処分者講習をどのタイミングで受講(仮免前、仮免後)するかを確認すると良いでしょう。仮免許取得前に受講する必要がある場合、講習を受ける前に教習所を卒業することはできません。また、講習が終わってからでなければ入校受付を行っていないところが多く注意が必要です。
運転免許再取得の流れ
再取得の流れは以下の通りです。
行政処分執行
(欠格期間開始)
取消処分者講習の受講
欠格期間満了
免許センターで試験に合格
免許の交付
上記の流れの中で、注意すべき点は欠格期間の満了日を正確に把握することと、処分者講習の受講タイミングと受講回数です。
欠格期間の正確な満了日は通知書で確認することができます。また警察署や運転免許試験場でも確認可能です。
処分者講習の受講タイミングと受講回数は、個々のケースにより変わります。こちらも正確な段取りが必要ですので、警察署や免許センターで確認しましょう。
- 確認事項
- 講習の受講回数は何回か?
- 講習の受講タイミングは、仮免前か仮免後か?
上記の2点を確認し、免許取得までの段取りを進めましょう。
指定教習所を卒業して免許取得を目指す場合
取消処分後に運転免許を再取得する場合は以下の2つの方法があります。
- 指定教習所を卒業後、運転免許試験場にて試験を受講
- 運転免許試験場にて一発試験を受講
一発試験は早く合格する事が出来れば時間と費用を大きく節約できる可能性があります。
一方で合格率が低く、結果的に教習所に行った方が安くなるケースが多く主流の方法ではありません。大きなリスクはありますが、先ほどもお伝えした通り時間と費用を大きく節約できる可能性があります。
ここでは指定教習所を卒業する場合を詳しくご紹介します。これから運転免許の再取得をする方は必読です。
事前に確認しておくこと
欠格期間の正確な満了日
欠格期間(免許の交付が出来ない期間)が残っている場合は、運転免許の取得ができません。免許の再取得の際に、各教習所では以下の4つのパターンに方針が分かれています。
- 欠格期間が満了してから受付が可能な教習所
- 欠格期間が満了してから入校が可能な教習所
- 欠格期間中に入校が可能な教習所
(残期間は教習所により異なります) - 過去に行政処分の経歴がある場合は合宿免許で入校が出来ない教習所
行政処分歴がある方は、自動車学校へ入校する(または申込み)をする際に欠格期間を聞かれるでしょう。その際に正確な満了日を回答できなければ申込が出来ない事もあります。
免許の匠でお手配させていただく合宿免許の場合も、過去に行政処分歴がある方は欠格期間の満了日をお伺いさせていただきます。事前にご確認いただければスムーズにご案内ができます。
取消処分者講習の受講タイミング
◎仮免前に受講する場合
仮免前に受講する場合は、自ずと教習所へ入校前に処分者講習を受講することになります。講習終了証書の有効期限は1年間ですので、早く受講しすぎて期限が切れないようにしましょう。
◎仮免後に受講する場合
仮免後に受講する場合は、教習所で2段階目に入ってから受講することになりますので、合宿免許では一時帰宅ができないため教習所を卒業後に受講します。
指定教習所に申込み
通学も合宿も同様に「欠格期間の満了日・取消処分者講習の受講タイミング」を確認後、入校できるかを教習所へ問合せましょう。その後は教習所の方針に則り、入校時期などを決めていきます。
免許の匠でご紹介させていただいている各教習所のよくある方針をご紹介します。
- 欠格期間満了後に申込みが可能
- 欠格期間満了後に入校が可能
- 欠格期間中に入校が可能(※)
- 行政処分歴がある方の入校は不可
満了日から1カ月前の教習所が多いです
再取得時の注意点
指定教習所を卒業して免許取得する場合
運転免許の取得に関しては全て自己責任
正確な欠格期間満了日を確認することや、取消処分者講習の受講タイミングの確認をすることは確実に免許の取得をするために必要なことです。
欠格期間の勘違いや、処分者講習の受講タイミングの認識違いにより、教習所の卒業証明書が無効になってしまうケースが過去にありました。こういった事故が過去に多く発生したため、自己責任ではあるものの、各教習所で受け入れ方針を設ける様になった経緯があります。
普通免許で運転できる車両サイズが違う
法改正により普通車で乗車できる車両のサイズが異なります。現在取得できる普通車の免許は過去の普通車の免許よりも乗車できる車両が小さくなっていますので注意しましょう。
簡単に説明すると、過去の普通車では2tなどのトラックの運転が可能でしたが今の普通免許では出来ません。取消処分を受けた方が再取得する場合、法改正後の普通免許を取得します。
知らずに運転してしまうと無免許運転となってしまいます。トラックなど大きめの車両を運転する場合は上位免許の取得をご検討ください。
実際に運転する車両の車検証をご確認の上、取得免許をご検討することをおすすめします。
準中型免許・中型免許・大型免許の取得について
準中型免許
- 免許経歴 必要なし
- 車両総重量 3.5t以上7.5t未満
- 最大積載量 2t以上4.5t未満
- 乗車定員 11人未満
多くの2tトラックを運転できる免許です。車両によっては運転できないトラックもありますので必ず乗車予定の車検証を確認しましょう。
中型免許
- 免許経歴 2年以上
- 車両総重量 7.5t以上11t未満
- 最大積載量 4.5t以上6.5t未満
- 乗車定員 30人未満
多くの2tトラックを運転できる免許です。車両によっては運転できないトラックもありますので必ず乗車予定の車検証を確認しましょう。
大型免許
まとめ
取消処分(行政処分)を受けた方の運転免許再取得について解説しましたが、かなり複雑でケースにより異なる為に大変難しい内容だったかと思います。
取消処分になった違反の内容によって、処分者講習の内容が変わる事もあります。不明点は必ず警察署、または運転免許センター・運転免許試験場に確認をしながら再取得を進めていきましょう。
運転免許の再取得は合宿免許がオススメ
通学と合宿の一番の違いは、費用と期間です。普通車ATでは最短14日間で卒業できますし、閑散期であれば20万円代の合宿プランもあります。
繁忙期(7月中旬~9月中旬、1月下旬~4月上旬)の時期は予約を取りにくく、費用も30万円から40万円を超えるプランもあり、日程をある程度調整可能な方は閑散期での入校を検討する事をおすすめします。
この繁忙期と閑散期は、予約を取るのが難しいのは通学も同じです。繁忙期での免許取得をお考えの方は少しでも早めに予約を確定すると良いでしょう。
これから運転免許を再取得を合宿でご検討の方は是非当社にお問合せください。
一人一人の状況をヒアリングさせていただき、ご希望に沿えるプランをご紹介いたします。
普通車の合宿免許・格安オススメ情報をチェック
合宿免許に関わるご相談を承ります
合宿免許を利用することで、短期での免許取得が可能です。
普通車免許以外にも、バイクやトラックの免許も取り扱いしております。
▼ ご希望の条件を入力するだけでスタッフがご提案 ▼
関連情報
合宿免許を知ろう
- 合宿免許とは?メリット・デメリットを通学と比較
- 合宿免許の値段・費用はどのくらい安いの?相場を決める条件は?
- 合宿免許の最短期間・日数は何日?最短合格率・卒業までの平均期間も解説
- 合宿免許に出会いってあるの?場所や条件は?
- 合宿免許の安い時期
- 免許取得に関わるよくある質問
- 合宿免許のモデルスケジュール(普通車AT)
- 合宿免許の車種別最短教習時間一覧
合宿免許の申込みにあたって
合宿免許への出発にあたって
合宿免許に役立つ情報
- 大学生におすすめの合宿免許を厳選
- 合宿免許の人気ランキング【卒業生レビューを掲載】
- 合宿免許体験記:小浜自動車学校(普通車)
- 合宿免許体験記:大宮自動車教習所(普通車)
- 【瀬見温泉・旅館喜至楼(きしろう)】体験レポート
- 合宿免許・運転免許・車に関する用語集
- 【合宿免許】卒業生の口コミ・レビュー
- 【合宿免許】新型コロナウイルス感染予防への取組と注意事項
- 合宿免許での運転に適した服装とは
- 免許取消処分(行政処分)を受けた方の再取得
- 全国の運転免許試験場一覧
- 合宿免許ローン支払いをお考えの方必見!
- 運転免許の試験問題集
- 合宿免許の賢い選び方。後悔しない選択をするには?
- 合宿免許って暇?空き時間のおすすめ暇つぶし方法
- 合宿免許の1日の流れを徹底解説
- 合宿免許はおすすめしないと言われる理由を徹底解説
- 合宿免許はきついって本当?きついと言われる原因と対策も解説
- 合宿免許の合格率は?最短で合格するには?
その他合宿免許のお役立ち情報