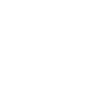- 免許の匠トップ
- 合宿免許・運転免許・車に関する用語集
合宿免許・運転免許・車に関する用語集
合宿免許・運転免許・車の用語集です。合宿免許の事で分からない言葉が出てきたら、このページでチェック!300語以上のキーワードを網羅しています。
合宿免許の用語(あ~お)
あ
| 合図 | 右左折、転回、徐行、停止、後退、進路変更を行う際に、手か灯火かウインカー(方向指示器)で行わなければならないもの。 右左折は30m手前、進路変更はそれを始める3秒前。 |
|---|---|
| アイドリング | 「idle」とは怠けると言う意味。 アクセルペダルを踏まずエンジンが低回転している状態。 アイドリングをやめれば自動車排ガスや騒音を出さないだけでなく、車の燃料も節約できる。 |
| 隘路への進入 | 中型・大型の一種・二種共通の第一段階で習う項目で、修了検定の一つにもなっている。 右折又は左折で進入路(幅6m)からはみ出さないように進入し、止まる事なく90度方向を変え、幅3m、長さ12mに引かれた2本のラインの範囲に車体を収める項目。 |
| アウトバーン | ドイツの高速自動車道で、ヨーロッパにおける主要幹線道路の一つとして有名。 |
| 青切符 | 交通切符の一つで、「交通反則告知書」のこと。比較的軽微な道路交通法違反をした運転者に対して交付され、反則金を納めることになる(納めない場合は刑事処分の対象となる場合あり)。 |
| 赤切符 | 交通切符の一つで、「告知票・運転免許保管証」のこと。行政処分点6点以上の重度の違反(飲酒運転など)や人身事故に対して交付されるもので、刑事処分の対象となり、罰金を支払うことになる。 |
| アクスル | 車軸、つまり車輪を回す際の中心の棒のこと。アクセルと間違えない様に注意。 |
| アクセル | 自動車で、エンジンの回転数を増やす事によって加速するための装置。四輪車はペダルで、二輪車はハンドルのグリップ操作できるようになっている。 類語・対義語 ブレーキ |
| アフターファイヤー | エンジン内で燃えきらなかったガスが排気管の中で大きな音を出して爆発する現象。 吸気が濃すぎて燃焼しきれない、吸気が薄くて発火しない、プラグから火花が飛ばない等、 空気とガソリンの混合比率や点火の不具合によって生じる。 |
| アームレスト | 乗員が車の中で楽な姿勢がとれるように設けられたひじ掛け状のもの。 一般的にはドアの内側に取り付けられている。 |
| アメリカン | 長く低いフォルムとV型と呼ばれるエンジンが特徴のバイク。 手足を前に投げ出すようなゆったりした乗車姿勢で乗るため、カーブの少ない道路をのんびりツーリングするのに向く。 |
| アルミホイール | 文字通りアルミを素材にした車輪。軽量な事が特徴。 ワンピースホイールとツーピースホイールがある。ワンピースホイールは単体で作られ、価格が安いが簡単なデザインしか作れない。それに対しツーピースホイールは価格が高くなるが複雑なデザインにも対応できる。 |
| 安全運転管理者 | 乗車定員11人以上の自動車を1台以上またはその他の自動車を5台以上所有する事業所等ごとに、自動車の安全に必要な業務を行わせるため、一定の資格要件を備えた者のうちから選任し、公安委員会に届け出た者。 |
| 安全地帯 | 路面電車に乗り降りする人や、道路を横断する歩行者の安全を図るために、道路上に設けられた島状の施設や、標識と標示によって示された部分をいう。 青地に白いV形を描く四角い交通標識で、安全地帯があることを示す。 |
| アンダーステア | 自動車が旋回するとき、ハンドルの切れ角が一定であるにもかかわらず、車の回転半径がだんだん大きくなってカーブの外側にそれていく現象。 |
| アンダーミラー | 主に中型車・大型車に取り付けられる、前方の足元など下方の死角を確認するためのミラー。 |
い
| イグニッションキー | エンジンを作動させるための鍵。差し込んで回すことで電気が通りエンジンがかかる。 イグニッション(ignition)とは点火、発火、点火装置の意味。 |
|---|---|
| 一時帰宅 | 免許合宿の期間中に、一旦帰宅すること。 対応不可な自動車学校もあるため注意が必要。 |
| 一時停止 | 走行中の自動車などが標識に従って、いったんその場に止まること。 これを行わなかった場合、違反にカウントされる。 |
| 一方通行 | 矢印の向きの流れの一方通行の道路である事を意味する。 一方通行の出口付近では「車両進入禁止」の標識を設置するのが通常。 車両の流れを変更する事によって、交通事故や交通渋滞を緩和しようという意図がある。 |
| 違反行為 | 違反行為は比較的軽微な違反(一般違反行為)と重大な違反行為(特定違反行為)に大別される。違反の種類によって、つけられる罰点も大幅に変わる(特定違反行為の方が大きい)。 |
| 違反者講習 | 運転免許を所持する者が一定の軽微違反行為をし、ある一定の基準(道路交通法第102条の2の政令で定める基準)に該当する事となった者に対する講習である。 この講習を受けなければ運転免許の停止処分を受ける事となる。 |
| イモビライザー | 自動車盗難防止のための装置の一つ。鍵と車両の双方にある装置からの暗号が一致しないとエンジンがかからず動かなくなるという仕組みである。 |
| インジケーター | 運転席の前の計器類の方向指示器や警告燈などのランプのこと。 |
| インターチェンジ (IC) |
高速道路などと一般道を結ぶため、互いの道路を立体的に交差させ、連絡路で結んだもの。高速道路同士のものをジャンクション(JCT)と呼ぶ。 |
| インテークマニホールド | エンジンに空気を送り込むための、多数に枝分かれした管。 低速回転のエンジンでは管が長い方がよく、高速回転のエンジンでは管が短い方がよい。 |
| インパネシフト | シフトレバーが計器盤(インストルメントパネル)にある事を指す言葉。 シフトの取っ手がハンドルに近いところにあるのでシフトチェンジ時の操作性に優れ、さらにコラムシフトに比べギアポジションが判りやすく、操作性もフロアシフト並みに良いという利点がある。 類語・対義語 コラムシフト フロアシフト |
う
| ウインカー | 方向指示器 |
|---|---|
| 運転 | 道路で車などをその本来の用い方に従って用いる事をいう。 自動車教習所内は道路にならないので、所内の練習は「運転」にはならない。 また二輪車をエンジンを止めて押して歩くときも「運転」にはならない。 |
| 運転免許 | 運転に一定の技量が必要な機械装置や設備の運転を認める許可をいう。 免許の保有を証明して交付される公文書を運転免許証という。 |
| 運転免許試験場 | 自動車運転免許の新規交付・更新・記載事項の変更を行う機関。 各都道府県公安委員会の管轄にあるが、実際の業務は法令の委任により警視庁及び道府県警察本部が行っている。 免許を取得する際、原則として自身が住民票を置いているところの運転免許試験場から運転免許証を発行してもらう事になる。 |
| 運転免許申請書 | 運転免許の申込書の事で、試験場で貰える。 必要事項を記入した上で必要額分の証紙を貼って提出する。 必要金額を渡し、証紙を貼った状態の用紙を受け取る場合もある。 |
え
| エアバッグ | 名前の通り空気の入ったクッション。車が衝突したときに膨らみ、搭乗者にかかる衝撃を和らげる。 ただし、正式名称であるSRS(=補助拘束装置)の通り、シートベルトの機能を補助するものでしかないので、運転時にはシートベルトをしっかり締める必要がある。 |
|---|---|
| エアブレーキ | タンク内に蓄えられた圧縮空気をペダルで送り込むことで作動するブレーキのこと。自動車では大型自動車に用いられる。 その仕組み上、ブレーキペダルの踏み込みやゆるめ操作を必要以上に繰り返してはならない。 日常点検においては、空気圧力計、ブレーキバルブの排気音、エアタンクのたまり水のチェックが必要である。 |
| エンジン | 動力機関のこと。 一般に内燃機関を指す事が多い。 |
| エンジンブレーキ | 加速時とは逆に車輪でエンジンを回し、エンジンの回転抵抗を利用して減速する手段の事である。 機関ブレーキとも呼ばれ、主に自動車等で用いられる言葉である。 一般のブレーキとは異なり「エンジンブレーキ」という装置がついているわけではなく、独立したペダルやレバーのようなものもない。 |
| エンスト | エンジンの回転が止まること。 エンジンの力よりも車の力が大きいと起こる。 |
お
| 追い越し | 車が進路を変えて、進行中の前の車両等に追いついた車両の側方(原則は右側車線)を通過し前方に出ること。前の車の動き(追い越しを行う・右折など)や場所(曲がり角付近やトンネル等)によって禁止されることがある。 |
|---|---|
| 追い抜き | 車両が進路を変えずに、進行中の車両等の側方を通過し前方に出ること。上記の「追い越し」に当たらない状態を指す。 |
| 応急救護 | 交通事故に遭遇した際に、居合わせたドライバーが適切な救護措置を講じる事ができるよう、指定自動車学校で行われる教習のこと。 医師・歯科医師・保健師・助産師・看護師・準看護師・救急隊員等は免除となる。 |
| 横断歩道 | 歩行者が道路を安全に横断するため、道路上に示された区域の事である。 歩行者と車両の両方から見やすいように、舗装面に白色のペイントによる縞模様が描かれたものが多い。 |
| 大型自動車 | 小型特殊自動車・大型特殊自動車・普通自動二輪車・大型自動二輪車以外で次のいずれかに該当する自動車。 車両総重量が11t以上のもの、最大積載量が6.5t以上のもの、乗車定員が30人以上のもの。 |
| 大型自動二輪車 | 総排気量が400ccを超える二輪車(側車付きのものを含む)の最高峰。 車両価格が比較的高価であり、車検が必要、燃費が良くない、維持費の負担が大きいなど、日常利用には必ずしも向いているとは言えず、維持所有のためのハードルは高い一方、パワーにあふれ、所有欲を満たす、趣味性の高い乗り物といえる。 |
| 大型特殊自動車 | カタピラを有する自動車やロードローラなど特殊な構造の自動車で、小型特殊自動車以外のもの。 |
| 押しがけ | バッテリーが上がった時、車体を押すことでエンジンを起動させる技術。MT車で使うことが出来る。 ギアを2にしてクラッチを切りつつ、タイヤが回転する力を使ってエンジンを起動させ、勢いがついたらクラッチをつなぐ。 |
| オートマチックトランスミッション | 自動車やオートバイの変速機構の一種で、車速やエンジン回転数に応じ、変速比を自動的に切り替える機能を備えたトランスミッション(変速機)の総称である。 類語・対義語 マニュアルトランスミッション |
| オドメーター | 走行距離計。 車ができてから何キロ走っているかを示している。 類語・対義語 タコメーター |
| オーバーステア | 自動車が旋回するとき、ハンドルの切れ角が一定であるにもかかわらず、車の回転半径がだんだん小さくなっていく現象。 |
| オーバーヒート | エンジンが高温になり、冷却水ではエンジンが冷やせなくなる状態。 そのままにしておくと、エンジンが焼き付いて止まってしまう。 |
| オービス | 速度違反自動取り締まり装置のこと。俗に「ねずみ取り機」と呼ばれる。 カメラとセットで道路に設置され、速度超過の車の速度と写真を記録する。 速度超過があった場合、後日警察から違反者に通知が来る。 |
| オフロード | 舗装されていない道。このような道路を走れるよう工夫された車両がある。 |
合宿免許の用語(か~こ)
か
| 外国免許切替申請 | 有効な外国の運転免許証を所持している者、資格のある者は運転免許試験の一部を免除して日本の運転免許を取得する事ができる。 略して「外国免許切替申請」と呼ばれる。 |
|---|---|
| カウリング | 自動二輪車を覆う、流線形のカバー。空気抵抗を減らし、操縦者やエンジンが抵抗にさらされることを防いだり、出せるスピード を上げたりするために存在する。 このカバーを持たない自動二輪車を「ネイキッド」という。 |
| カウンターステア | 後輪が滑ったとき、その滑る方向にハンドルを切ること。 進行方向と逆にハンドルを切ることになるので、逆ハンドルともいう。 一般道路の滑りやすい道やモータースポーツの高速走行時に行われる。 |
| 加速車線 | 高速道路において、ジャンクションやサービスエリアから、車を加速しつつ本線へ合流させるための道路。 本線を走る場合、この付近では流入する車に要注意である。 |
| 学科教習 | 実際に運転するにあたり必要な知識を技能教習の進度に合わせ、2段階で実施する。 1段階では、信号標識、安全運転、免許制度等、基本的な事を教習する。 2段階では、危険予測、応急救護等、より実践的な運転に伴う知識を教習する。 |
| 合宿免許 | 一定の期間に教習所の宿舎やホテル、ペンション等に滞在して、 運転免許取得のための教習を集中して受けること。 |
| カースクール | 自動車学校 |
| カーナビゲーションシステム | 電子的に自動車の走行時に現在位置や目的地への経路案内を行なう機能をもつ電子機器。 略して「カーナビ」と呼ばれる事が多い。 |
| カブリオ | オープンカーの一種。屋根が幌状(布やビニールでできていて、折りたためる)になっている。 その中でも、特にサイドウインドーがなく二人乗りの車をロードスターと言う。 アメリカではコンバーチブル、イギリスではドロップヘッドクーペという。 |
| かもしれない運転 | 安易な予測による思い込みをなくし、自分にとって悪いケースを想定しながらそれに備えた運転をすることを表す言葉。運転中の危険察知において重要となる。 逆のパターンを「だろう運転」という。 |
| 仮運転免許 | 免許の取得を目指す者が、公道上で運転練習・教習を行ったり、路上の技能試験・技能検定等を行う際に必要となる免許。略して「仮免許」や「仮免」と呼ばれる。 種類には普通車用の普通仮免、準中型車用の準中型仮免、中型車用の中型仮免、大型車用の大型仮免がある。そのため、現在自分が所持している免許より大きい車種の免許を取る場合(限定解除は除く)、一種・二種問わず仮免許の段階を踏むことになる。 |
| 仮停止処分 | 免許停止処分の一つで、危険性の高い悪質な事故を起こしたとき、事故を起こした日から最長で30日間下される。 仮停止処分を受けた人が、その後本格的に免許停止になった時、仮停止期間も停止期間に通算される。 類語・対義語 免停 |
き
| キックスターター | 自動二輪車で、ペダルを踏んでエンジンを始動させる装置。 |
|---|---|
| キックダウン | オートマチックトランスミッションを搭載した自動車でアクセルペダルを大きくあるいは急激に踏み込んだ場合に、より低速なギアに切り替わる機構を言う。 さらにはその現象や意図した操作を指す場合もある。 |
| 軌道敷 | 路面電車が通行するために必要な道路の部分で、レールの敷いてある内側部分のこと。軌道敷とその両側0.61mの範囲は駐停車禁止となっている。 |
| 技能教習 | 運転の技術を教える教習。 指定自動車学校では、1段階で基本的な運転操作を学校コース内で練習し、仮免許取得後に2段階として、路上においてより実践的な運転操作を練習する。 |
| 技能修了検定 | 指定自動車教習所で仮運転免許を取得する際に、本来運転免許試験場で行われる仮運転免許技能試験を免除の扱いとするために、指定自動車教習所内で行われる運転技能についての検定の事である。 自動二輪車、大型特殊自動車、けん引は修了検定は行われず、卒業検定まで場内で教習が行われる。 類語・対義語 卒業検定 |
| 技能卒業検定 | 運転免許を取得するために、指定自動車教習所を卒業する際に、最後に必ず行われる技能に関する試験の名称。 この試験に合格すると、指定自動車教習所を卒業した事になり、卒業証明書を運転免許試験場に持参すれば、運転免許試験場での技能試験が免除される。 |
| 技能審査合格証明書 | 各種免許のAT限定・中型免許の8t限定・大型免許のマイクロバス限定・自衛隊車両限定等、運転できる自動車等に限定が付いていて、この限定を教習所で解除する場合、規定の教習を終えた後卒業検定に合格すると交付される。 技能審査合格証明書は合格した日から起算して3か月間有効である。 |
| キャブレター | ガソリンと空気を混合し、混合気を作る装置。 |
| 教習所 | 自動車学校 |
| 行政処分 | 過去の違反に関して行政の処分を受けること。 免許の停止と免許の取り消しの2種類ある。 類語・対義語 免停 免取 |
| 共同危険行為 | 二台以上の自動車が道路で走行する際に、他の車に迷惑を及ぼしたり危険を生じさせたりする行為。道路交通法で禁止されている。 |
| 緊急自動車 | 道路交通法では、救急用自動車や公安委員会が指定する警察・自衛隊用の自動車など、緊急用務のために運転中のものをさす。 |
く
| 駆動輪 | 自動車で、エンジンからの動力が伝わって車を動かす車輪。 駆動輪の仕組みによって前輪駆動(FWD)・後輪駆動(RWD)・四輪駆動(4WD)に区別される。 |
|---|---|
| クーペ | 自動車のボディタイプのひとつである。 クーペという単語はフランス語で「切られた馬車」を意味する。 2人乗りで2ドアの自動車のうち、固定された屋根を備える自動車を指す言葉として用いられてきたが、最近ではそれのみならず、スポーティなスタイルを持つ自動車という意味で、4ドア車にも用いられている。 |
| クラッチ | エンジンと変速機の間に存在し、発進・停止・変速などの時にエンジンのパワーを変速機に伝えたり遮断したりする役割をする装置。 ペダルを踏んで動力を遮断状態にすることを「切る」、その逆の操作を「つなぐ」という。 |
| クラッチスタートシステム | MT車において、エンジンが始動する時にクラッチペダルを踏んでいなければキーを回しても作動しないシステム。 MT車の誤作動を防ぐために存在する。 |
| クランク | 直角の狭いカーブが二つ交互に繋がっている道路のこと。 |
| クリープ現象 | アクセルペダルを踏む事なく、エンジンがアイドリングの状態で車両が動く現象のこと。 |
| クルーザー | ①バイクで、「ツアラー」と呼ばれているもの。 ②バイクで、「アメリカン」と呼ばれているもの。 |
| 車など | 交通用語で車と路面電車のこと。 |
| グローブボックス | 助手席の前にある小物入れ。 |
| グロープラグ | 内燃機関に用いられるエンジン点火装置の一つ。 点火栓を持たない内燃機関における、冷間時の始動を助ける補助熱源。 |
け
| 軽車両 | 日本の交通法規の用語で、原動機を有しない車両の総称である。 (自転車、荷車、リヤカー、そり、牛馬等。 身体障がい者用の車いすや小児用の車は歩行者として扱われる。) |
|---|---|
| 警笛 | 自動車や鉄道車両、船舶等において、自らが近づく事を音を使って他の通行対象に知らせるために使用する保安用具である。 |
| 欠格期間 | 免許の拒否・取消の処分に当たり運転免許を受ける事のできない期間のこと。 取消処分では、違反点数に応じて取消後の「欠格期間」が1年~10年定められており、この期間は運転免許の再取得ができません。 |
| けん引自動車 | 他の車をけん引するための構造や装置を備えた自動車。 日本の道路交通法の規定では、「牽引自動車」、「牽引車」とも牽引する側(トラクター)のみを指し、牽引される側の車両(車両総重量が750kgを超えるもので要牽引免許車輌)を「重被牽引車」としている。 |
| 原動機付自転車 | 道路交通法では50cc(0.6kW)以下、または総排気量125cc以下かつ定格出力4kW以下の二輪車が該当する。 いっぽう、道路運送車両法では125cc以下(1.0kW)の原動機を備えた二輪車(道路交通法上の小型二輪も含む)が該当する。 省略して「原付(げんつき)」と呼ばれる事も多い。 |
| 限定解除審査 | 各種の限定条件が付けられている免許(限定免許)を、限定条件のない免許に変更するための審査をいう。 AT限定解除・8t限定解除等。 |
| 眩(げん)惑 | 文字通り目が眩(くら)んでものが見えず、正しい判断ができなくなること。 運転においては、対向車のヘッドライトを目に受けたときに起こる。視線を前から少し左にずらすことでこの現象を防ぐことができる。 また、対向車とすれ違う際にヘッドライトをロービームに切り替えることで相手を眩惑させないことが求められる。 |
こ
| 効果測定 | 自動車学校で行われる学科試験。 |
|---|---|
| 交差点 | 2本以上の道が交わる場所。 道路交通法上は、「十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分」を指す。 |
| 更新 | 運転免許においては、有効期限の前にそれを更新する手続のこと。 違反歴・免許歴により、優良運転者講習・一般運転者講習・違反運転者講習・初回更新者講習のいずれかを受けなければならず、それに応じて更新手続ができる場所や手数料に差が出る事となる。 |
| 高速教習 | 高速道路を走行する教習のこと。 |
| 交通切符 | 交通違反の際に発行される切符の総称。 違反が重い順に赤切符・青切符があるが、主に赤切符をさす。 類語・対義語 点数切符 |
| 公認校 | 指定自動車教習所 |
| 高齢運転者マーク | 道路交通法に基づく標識の一つ。 70歳以上の運転者が運転する普通自動車に、努力義務で表示される。 |
| 高齢者講習 | 免許証の更新期間が満了する日における年齢が70歳以上の高齢者について、更新期間が満了する日の前6ヶ月以内に受講していなければならないと定められている講習。 受講前の運転適性指導を含め、加齢に伴って生ずる身体の機能の低下を高齢者に自覚させ、多分に因果を含める事を真の目的とするもの。 |
| 小型二輪車 | 道路交通法では総排気量125cc以下、または定格出力1.00kw以下の普通自動二輪車のこと。普通自動二輪免許に「小型限定」とある場合は、このサイズまでの自動二輪車しか運転ができない。 また、道路運送車両法上、定期点検整備の対象外となる。 |
| 小型特殊自動車 | 特殊自動車で、車体の大きさが一定サイズ以下のもののうち、15km/hを超える速度を出す事ができない構造のもの。略して「小特」という。 いずれかの条件を超えるものは大型特殊自動車となる。 但し、道路運送車両法上は、農耕作業用自動車は幾ら大きくても小型特殊自動車扱いになる。 |
| 国際運転免許証 | 日本だけでなくジュネーブ条約に加盟している国で自動車を運転するための免許証。 有効期限は発給の日から1年間。また、国や州によってその扱いが異なることがあるので注意。 外国運転免許とは異なる。 |
| 五点確認 | 大型二種を除く、全ての二種免許で必須とされている安全確認の基本手順を指す言葉。 一般的には、ルームミラー、左ミラー、左後方目視、右ミラー、右後方目視のそれぞれの確認を指す。 直接目視は左右それぞれの「後方」であって「側方」ではないので注意。 類語・対義語 七点確認 |
| コーナリング | 道路やサーキットコース等のカーブを曲がる事(行為)を指す。主にモータースポーツの世界で用いられる。 コーナリング時にタイヤが遠心力に負けずに元に戻ろうとする力(コーナリングフォース)がかかるので、車両がスリップしやすくなる。このため、自動車を操縦する(特にモータースポーツを行う)際にはコーナリングのテクニックが求められる。 |
| ゴールド免許 | 運転免許証の有効期限表示部分の地の色が金色であるものの通称で、優良運転者免許証とも表記される。 自動車運転免許の更新等をした時点で過去5年以内に減点対象となる交通違反などが確定していない優良運転者に与えられる運転免許である。 免許証の有効期限記載欄が金帯で表記され、黒枠で「優良」の文字が付記される。 1994年5月10日の道路交通法改正で導入された。 ゴールド免許は一般の運転免許に比べて免許の有効期間が長く、また(ゴールド免許となる)免許更新時に必要な講習時間が短く更新の手数料も安く済む利点がある。 さらに無違反を少なくとも5年間継続できたリスクの低いドライバーである事を簡単に証明できるため、自動車保険のうち多くの任意保険で保険料の割引制度がある。 |
| コラムシフト | シフトレバーがステアリングコラム(ハンドル軸)に配置されていることを指す。 シフトの取っ手がハンドルに近いところにあるため、操作性に優れるうえ、足元を広く利用できる。 逆に、AT車の場合は限られたレバー操作で多くのレンジを設定できないため、ギアの段数が多くなると操作性が劣るといった欠点もある。 類語・対義語 インパネシフト フロアシフト |
| 小回り右折 | 原動機付き自転車が自動車と同じく交差点を直接右折すること。対義語は二段階右折。 交通整理(信号や警官の手信号)が行われていない交差点は原則この方法で通り、交通整理が行われている場合、車両通行帯が2以下のもの(二段階右折の指示がない場合)と、両通行帯が3つ以上で小回り右折の標識がついたものがこの方法で通れる。 |
| コンバーチブル | カブリオ |
| 混合気 | ガソリン式エンジンにおいて、ガソリンなどの燃料を霧状にして、空気と混合したもの。 エンジンは混合気を燃やすことで動くので、エンジンを正常に動かすためにはガソリンと空気の比が重要になる。 |
合宿免許の用語(さ~そ)
さ
| 最高速度 | 法令の下で、車両がそれ以上の速度を出してはならないとする最高の速度。 各種交通機関などに対して法令で定められており、制限速度とも言う。 |
|---|---|
| サイドブレーキ | 手動式の制動機構を指す。 このため、ハンドブレーキとも称される。 自動車のブレーキ機構のひとつ。 最近では足踏み式の同種の機構が増えて来ているため、パーキングブレーキ・駐車ブレーキなどの表現で置換される事が多くなっている。 |
| サグ部 | 道路の下り坂から上り坂に切り替わる部分。車両の速度が低下しやすく、渋滞の原因となる。 |
| サスペンション | 二輪や四輪の自動車で、路面と車輪との衝撃を乗員に伝えないようにする装置。ばねの力を中心とした仕組みで作動する。 |
| サービスエリア (SA) |
高速道路等に概ね50kmおき(北海道はおおむね80kmおき)に設置される休憩施設の事である。 休憩・食事・自動車の給油・整備点検のための施設として設置される。 一般に駐車場・トイレ・無料休憩所・緑地・遊具施設のほか、レストラン・売店・情報コーナー・給油・修理所(ガソリンスタンド)などが設けられるのが普通である。 |
| サーモスタット | 冷却水の循環経路の途中に設けられ、水温が低いときは閉じて、水温が高くなると開いて冷却水をラジエーターに循環させてエンジンの温度調節を行う装置。 この装置が故障するとオーバーヒートしたり、逆にヒーターが効かなくなったりする。 |
| サルーン | 乗用車の形式のひとつで、前後2列に座席があり、4人~6人乗りのものを指す。乗用車では最も一般的な形式。 「サルーン」はイギリスでの呼び名であり、アメリカでは「セダン」、イタリアでは「ベルリーナ」と呼ばれる。 |
し
| 時間制限駐車区間 | 時間を限って同一車両が引き続き駐車する事ができる道路の区間である事が道路標識等により指定されている道路の区間。 |
|---|---|
| 時差式信号 | 交差点の信号機が「赤色」になる時間をずらした信号機。 右折車両を早く流す効果がある。 |
| 失効 | 更新期間内に運転免許証の更新をしなかった場合、有効期間の満了により免許は失効となる。 |
| 指定自動車教習所 | 公安委員会が、道路交通法第九十九条に基づいて指定した、自動車教習所(自動車学校)のこと。 指定自動車教習所を卒業すると、道路交通法第九十九条の五第五項の規定により、運転免許を取得する際の技能試験が免除される。 公安委員会から指定を受ける条件として、指導員等の人的基準、コースや教室などの物的基準、その他の運営基準の3つがあげられる。 類語・対義語 非公認校 |
| 指定方向外進行禁止 | 交差点の手前などに設置し、矢印の方向以外の進行が禁止されている事を表す。 |
| 自動式速度取締測定機 | オービス |
| 自動式ナンバー読取照会システム | Nシステム |
| 自転車 | 乗り手自身が車輪を動かす事を動力として、乗り手の運転操作により地上の進路を自在に走る乗り物のこと。 |
| 自動車 | 原動機を動力として陸上を走る車両のうち、レールによらず運転者の操作で進路や速度を変える事ができる乗り物のこと。 |
| 自動車学校 | 運転免許を受けようとする者に対して、自動車の運転に関する道路交通法規などの知識、そして運転に関する技術を教習させる施設である。自動車教習所や自動車学院も同じ意味である。 |
| シートアジャスター | 座席の姿勢を調整する装置の総称。 |
| シートベルト | 安全のためにからだを座席に固定させるベルト。 自動車・航空機には取り付けが義務付けられている。 |
| シートリフター | シートの高さを調節する機構。 |
| 自賠責・共済 | 万が一自動車の人身事故を起こした時に被害者に支払う損害賠償費を補てんするための保険。正式名称を「自動車損害賠償責任保険・共済」という。 自動車・バイクを保有している人は、法令のためこの保険を保有していなければならないほか、運転する際に紙の保険証を車両に備え付けるかスマホで電子保管する必要がある。 |
| シビアコンディション | 和訳した通り、自動車にとって一般的なものより「厳しい使用状況」のことを指す。 多くの場合自動車の製造者が定義しているが、頻繁に走行する道路の状態や、走行距離などが自動車にとって負担が大きいものである。 この状況に置かれた車は、メンテナンスをするべき周期が短くなる。 |
| シフトダウン | 自動車の運転中に、ギアを低速のものに切り替えること。 |
| シミュレーター | 高速道路や雪道など、実車を用いると危険が伴う可能性の高い場面の練習をするための模擬運転装置のこと。 また逆に、教習において通常運転される現実の車を実車という。 |
| 車検 | 道路運送車両法によって多くの自動車に義務づけられている、構造・装置・性能などの検査。 用途や構造によって1年、または2年ごとに受ける※。この検査を受けて自動車検査証を交付された車でなければ運転してはいけない。 定期点検 とは別である。 類語・対義語 定期点検 ※2年ごとに検査を受ける自動車のうち、二輪の自動車および自家用の乗用自動車(車両総重量8トン未満・乗車定員10人以下に限る)は、初回は3年。 |
| シャシー | 自動車の骨格となる部分で、自動車からボディ部を取り外した状態、つまり自動車のボディ以外のすべて。 |
| 車線 | 車道において車両が走る部分。車線の中でも白線や黄線により走行レーンが区分された道路部分を車両通行帯という。 走行車線、追越し車線、登坂車線、片側一車線等がある。 別の車線へ移動する事を車線変更と呼ぶ。 |
| 車道 | 通常、車両および路面電車が通行する道路の部分。 類語・対義語 歩道 |
| 車道外側線 | 車道の左端に引かれる白い実線で、車道の境界を示す。歩道のある道路ではこの線から歩道の縁石までの間も車道として扱われる。歩道がない場合はこの線を超えると路側帯となる。 |
| 車幅灯 | 車体の前後左右の端、合計4か所につけられる小さなランプ。文字通り、夜間運転する際に車幅を示す機能がある。 |
| 車両横断禁止 | 標識や標示により、車(軽車両含む)が横断するための場所である事が示されている道路の部分。右側に店舗や駐車場に入るような横断ができないことを示す際に使われる。 |
| 車両進入禁止 | 路における車両の通行につき一定の方向に対する通行が禁止される道路において、車両がその方向に進入する事を禁止すること。 |
| 車両通行帯 | 車が道路の定められた部分を通行するように標示によって示された部分。 |
| 車両通行止め | 車両の通行を禁止すること。 |
| 車両総重量 | 車の重量、最大積載量、乗車定員の重量(1人55kgとして計算)の総合計重量。 |
| 車輪止め装置取り付け区間 | 違法駐車に対して、車輪止め装置を付けて車両を動かせないようにした区間。装置のつけられた車には、更に車輪止め標章も付けられる。 その車の使用者・所有者・関係者のいずれかは、この区間を管轄する警察署長に申告して車輪止め装置を取り除いてもらわねばならない。 |
| 修了検定 | 技能修了検定のこと。さらに略して修検とも。 類語・対義語 技能卒業検定 |
| 重量制限 | 通行できる車両の重量制限を示す。 車両の自重の他、積載荷物の重量も合算した総重量で判断される。 |
| 縦列駐車 | 縦一列に停められた車の間や車が入る程の壁のくぼみなど、駐車枠に車体をおさめることで駐車すること。 |
| 準中型車 | 車両総重量3.5トン以上7.5トン未満、最大積載量2トン以上4.5トン未満のうちいずれかを満たす、乗車定員10人以下の車両。 |
| 消音器 | マフラー |
| 蒸発現象 | 夜間に、自分の車のライトと対向車のライトが重なる地帯で、歩行者や自転車が見えなくなること。 |
| ショートカット走行 | 交差点などを右折する時に、交差点の内側を斜めに通行すること。 右方向の死角が大きく、右折先の車と衝突しやすい。そのため、事故の際「早回り右折」として過失にカウントされることもある。 |
| 徐行 | 車がすぐに停止できるような速度で進行すること。 ブレーキを操作してから停止するまでの距離が概ね1m以内(目安として時速10km以下)の速度であるといわれている。 |
| 初心運転者標識 | 普通車免許の取得後1年を経過しない(免許の効力が停止されていた期間を除く)運転者が車両に掲示する義務がある標識。「初心者マーク」や「若葉マーク」と呼ばれている。 掲示場所は、車両の前後の視認性の高い部分(地上0.4 - 1.2m以内)である。 また、周囲の運転者はこの標識を掲示した車両を保護する義務があり、幅寄せ・割り込み(やむを得ない場合は除く)などの行為を行なってはならない(行った場合違反となる)。 矢羽のような形状をしていて、左が黄・右が緑に塗り分けられている。 |
| ジレンマゾーン | 信号機が黄色に変わったときに、行こうか止まろうか迷う範囲のこと。 ちなみに黄色は注意進行ではなく、基本的には「(安全に止まれるとき)止まれ」である。 |
| 白切符 | 点数切符 |
| シンクロメッシュ | MT車に備えられた、かみ合わせるべき歯車の回転速度をあらかじめ合わせることで変速を円滑にするための装置のこと。 |
| 信号 (信号機) |
鉄道や道路における交通の安全の確保、若しくは交通の流れを円滑にするために、進行・停止などの信号を示す装置である。 |
| 深視力 | 視力の中でも、立体感や遠近感を見分けるためのものをさす。 ドライバーの中では、準中型・中型・大型・けん引・二種免許を取得す る際必要とされる。検査は、三桿(かん)法奥行知覚検査器で3回行われる。 |
す
| スイッチターン (スイッチバック) |
バックで現在いる車道の外に入り、元の車道に出て、今までとは逆の方向に転回すること。 |
|---|---|
| スキッド教習 | 危険体験教習の一つ。 冬場の凍結道路・雪道道路などにおけるスリップの危険性、及びスリップ時の自動車の動きや操作方法を体験するための教習。 特殊な装置の取り付けられた専用の車両を用い、助手席の指導員のコントローラ操作により車輪を浮上させ、擬似的にスリップ状態を体験させる事ができる。 |
| スクーター | 足置き部分が平らになっているバイクのことで、ATバイクの多くがこの種類にあたる。 スクーターの中でも、排気量が250ccを超えるものを、ビッグスクーターという。 |
| スクールゾーン | 歩行者と車の通行を分けて、通学通園時の幼児・児童の安全を図る事を目的に、小学校や幼稚園などのおおむね半径500メートルの範囲で設定。 |
| スタッドレスタイヤ | 名前通り鋲を使わず、ゴムの材質や溝の形を工夫することで、雪道でも安定して走ることが出来るようになったタイヤ。 |
| スタンディングウェーブ現象 | 走行中、タイヤの後部が波状にたわみ、やがて発熱で瞬時に破裂してしまう現象。 タイヤが空気圧不足で高速走行したときに起こる。 |
| ステアリング | 乗り物の進行方向を任意に変えるためのかじ取り装置の事で、専門用語では『操舵装置』という。 小型船舶から、自転車、オートバイ、自動車から戦車にいたる陸上の車両まで広く使用されている。 |
| スパイクタイヤ | スリップ防止のために金属の鋲を打ち込んだ、雪道用のタイヤ。 道路まで削ってしまうため様々な弊害を生み、現在は特例を除いて禁止されている。 |
| スピードリミッター | ある一定以上のスピードが出ないように、エンジンの回転を制御する装置。 点火装置で制御するタイプと燃料をカットするタイプがある。 |
| スピンターン | タイヤを横滑りさせて車の向きを変えるテクニック。 |
| スポーク | 外周部分を支えているリムと、車輪の中心にあるハブをつなぐ金属線のこと。 基本的にはハブから放射状に伸びている。 |
| スラローム | 自動二輪車の訓練の一つ。等間隔に置かれたコーンを縫うように、リズミカルに切り返しながら走る。体重移動とアクセルの操作が成功を左右する。 白バイ大会や二輪教習などで行われる。 |
| スマートエントリー | 鍵を携帯しているだけで、近づけば鍵が開き遠く離れれば鍵が閉まるシステムのこと。主に自動車などに用いられる。 |
| スリーター | 自動車の一種。スクーターのようで、車輪は前一つ後ろ二つ、計三つの車輪を持つもの。 |
| スリップサイン | タイヤが磨り減っている事を示すところ。 タイヤの横の一番外回りを見ると△が記されている。 タイヤが磨り減るとまずこの部分の溝がなくなってわかるようになっている。 スリップサインが表れた車は、整備不良車として処罰の対象になる。 |
| スロットル | ガソリンエンジンにおいて、エンジンに吸入される空気量を絞ることにより調整する部位のこと。 この部位によってエンジンの回転数と負荷を調節する。アクセルをいっぱいにかけると、スロットルも全開(フルスロットル)になる。 |
せ
| セダン | サルーン |
|---|---|
| セパレート信号 | 矢印式信号機の一種。青の矢印信号だけで交通整理を行い、文字通り右折・左折・直進の流れるタイミングを分けている。 矢印を見落とさないよう注意が必要となる。 |
| セミAT | 自動車のトランスミッションの一つ。 四輪車の場合、ギアはMTのように手動で変速を行うが、クラッチはATのように自動で行われる。 ペダルが2個しかなくなるので、2ペダルMTともいわれる。 類語・対義語 オートマチックトランスミッション マニュアルトランスミッション |
| セルモーター | エンジン始動のためのモーター。 このモーターを使ってエンジンを始動させることを「セルフスターター」という。 |
| 前照灯 | 輸送機械などに搭載し、操縦者の視認性と外部からの被視認性を向上させるために使われる照明装置である。 |
| センタースタンド | バイクを駐輪する際に立て、バイクを安定させるための部品。文字通り車体下部の中心に取り付けられる。 このスタンドを平地で楽に立てられるかがバイクを選ぶ基準となる。 |
そ
| 走行距離計 | オドメーター |
|---|---|
| 総排気量 | エンジンの大きさを表わすのに用いられる。 数字が大きいほど大きなエンジンになる。 |
| 側道 | 高架やトンネルなど、出入りが制限される道路に隣接・並行して設けられる道路のこと。 幹線道路の側道の場合、その先で立体交差する道路への右左折用途である場合もある。 |
| 側方間隔 | 特に路上において、側方通過時に色々なモノとの間に保たなければならないもの。 運転免許技能試験において、電信柱や標識柱のような固定物については0.5m、可動物と対面で(相手がヒトの場合は気が付いている状態で)すれ違う場合は1m、可動物を後方から抜く場合(ヒトの場合は気が付いていない状態)は1.5m保たなければ大変危険とされる。 |
| 側方通過 | 対向車と行き違うこと。対向車と安全な間隔を取ることが必要になる。。 |
| 卒業検定 | 技能卒業検定のこと。さらに略して卒検とも。 類語・対義語 技能修了検定 |
| 卒業証明書 | 指定自動車教習所において教習課程を全て修了し、卒業検定に合格した者に公布される書類。 卒業後に運転免許試験場で運転免許試験を受験する際、卒業証明書を提出すれば、運転免許試験場での技能試験が免除される。 卒業証明書は卒業検定の合格日より一年間有効であるが、原則再交付不可なので、紛失等には要注意である。 |
合宿免許の用語(た~と)
た
| 第一段階 | 自動車教習の二段階制において、先に行うもの。 技能教習では教習所内で基本操作及び基本走行を学び、学科教習では路上で運転する時の基礎知識を学ぶ。この段階で技能・学科試験(修了検定)をクリアすると、仮免許公布となる。 |
|---|---|
| 第一種免許 | 日本における道路交通法上の免許区分のひとつ。 自動車や原動機付自転車を一般的な目的で運転する場合に必要な免許である。 類:第二種免許 |
| 代行運転自動車 | 酒気帯びなどの事情があって運転出来ない客に代わって専門の業者が運転する、顧客の車。 運転する際には二種免許が必要となるほか、運転中には専用のマークを前後の見やすい位置につける必要がある。 |
| 大特 | 大型特殊自動車 |
| 第二種免許 | 日本における道路交通法上の免許区分のひとつ。 バスやタクシーなどの旅客自動車を旅客運送のため運転しようとする(営業ナンバーの乗用自動車で、旅客を乗せて商業的な活動をする)場合や、運転代行の業務として自動車を運転する場合、すなわち旅客運送契約遂行として自動車を運転する場合に必要な運転免許である。 類:第一種免許 |
| 第二段階 | 自動車教習の二段階制において、後に行うもの。 技能教習では実際の路上や高速道路(こちらはシミュレーターの場合有)での教習が行われ、学科教習では第一段階の学習を踏まえて運転時の危険要因や特殊な状況下での運転について学ぶ。また、応急救護や安全運転ディスカッションが行われるのもこの段階である。 この段階で技能・学科試験(卒業検定)をクリアすることで卒業となる。 |
| ダイバーシティアンテナ | アンテナを複数使用し、もっとも強い電波を受信しているアンテナに自動的に切りかえるシステムのアンテナ。 |
| タイヤ | 車輪のリムを丸く囲む帯状の構造で、路面・地面あるいは軌道の上を転がる踏面(トレッド)を形成するものの総称。 |
| タイヤチェーン | 雪道でのスリップ防止のために、タイヤに特定の方法で巻きつけられる鎖。鎖は駆動輪に巻きつけられ、クリップ付きのチェーンバンドなどで固定される。 |
| 待避所 | せまい坂道において、行き違いになることを防ぐために少し道幅が広くなった場所を指す。 近くに待避所がある場合、上り坂であっても待避所がある側の車が道を譲ることになる。 |
| タコメーター | 一般に回転計といわれているエンジンの回転速度を表す計器。 類語・対義語 オドメーター |
| 立ちごけ | 二輪車を操作する際に、二輪車にまたがった状態でバランスを崩して転倒すること。 停止したり低速で走行したりするとき、足の着きが悪いと起こりやすくなる。 |
| ターボチャージャー | エンジンの補助装置の一種。エンジンが動く時に出る排気ガスを利用してタービンを回し、シリンダー内に混合気体を圧縮して送り込む。 燃費の効率化などのメリットがある。 |
| ダンプトラック | 荷台を傾けて積載物を重力で滑り降ろす構造のトラックを指す。「ダンプカー」ともいう。 最も広く利用されている運搬用機械で、骨材、コンクリートなどの運搬に使用される。 公道上を走れるものとそうでないものがあり、 区別するときには公道上を走れるものを普通ダンプトラック、 そうでないものを重ダンプトラックと呼ぶ。 |
ち
| チャイルドシート | 安全を確保するため身体を座席に固定する、子供専用の車載用装置のこと。 平成11年6月より6歳未満の子供に装着を義務付けられた。 さらに平成12年4月より反則点数と反則金の適用が開始となった。 |
|---|---|
| チャイルドロック | ドアを内側からは開けられないようにするシステム(外側からは開く)。 走行中に子供が不用意にドアを開けないように採用されている。 |
| 中央線 | 対面通行での対向側との境界線。 交通量が多い首都圏の一部の道路では朝と夕方で中央線の位置が変移する道路(リバーシブルレーン)もあり、その場合は矢印標識で位置が現示される。 |
| 中型車 | 小型特殊自動車・大型特殊自動車・普通自動二輪車・大型自動二輪車以外で次のいずれかに該当する自動車。 車両総重量が7.5t以上11t未満のもの、最大積載量が4.5t以上6.5t未満のもの、乗車定員が29人以下のもの。 類語・対義語 特定中型自動車 |
| 駐車 | 車の継続的な停止(人の乗り降りや、5分以内の荷物の積み下ろしの為の停止を除く)や、運転者が車から離れていてすぐに運転できない状態の停止をいう。 運転席に運転手がいても継続的な停止をした場合、駐車になる。 類語・対義語 停車 |
| 駐車違反 | 駐車禁止の場所・時間帯に駐車を行った場合、違反となる。 |
| 駐車余地 | 車両の右側の道路(車道)上3.5メートル(「駐車余地」の道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないような場合、駐車してはならない。 |
| 駐停車禁止 | 駐車も停車もしてはならないこと。 |
| チルトステアリング | ハンドルの傾きを調節する機構。 |
つ
| ツアラー | 快適に長距離を移動できるように作られたバイク。楽な姿勢で乗れるようにしたり、カウリングを付けて風の抵抗を防いだりといった工夫がなされている。 |
|---|---|
| 通学免許 | 地元の教習所に通いながら、運転免許取得を目指す方法。 |
| 通行止め | 道路が事故、災害、気象条件の悪化、工事などのために道路管理者や警察の判断により通行できなくなること。 |
| ツーリング | オートバイを使って移動する事を主軸とした旅行である。 |
て
| 定期点検 | 一定以上の出力または排気量を持つ自動車が、文字通り一定期間(期間は車両のサイズや出力によって異なる)で、認定された期間によって行われる、法規に基づいた点検。 車検とは別である。 類語・対義語 車検 日常点検 |
|---|---|
| 定格出力 | 自動車では、モーターが良い条件で安定して出せる最大の出力のことをいう。単位はkw。 |
| 停止距離 | 運転者が危険を感じてからブレーキを切り、車が完全に停止するまでに車が走る距離。 大きく二つに分けられ、運転者が危険を感じてからブレーキが実際にきき始めるまでの距離を空走距離、ブレーキがきき始めてから停止するまでの距離を制動距離という。 |
| 停止禁止部分 | 前方の交通状況によって停止する恐れがある場合進入してはいけない場所。 警察署や消防署などの前につけられる。 |
| 停止線 | 車両の停止位置を示す必要がある地点で、車両が停止する場合の位置である事を示す標示。 主に交差点などで、先頭車両が停止するべき位置を示すものである。 |
| 停車 | 駐車にあたらない短時間の車の停止を指す。 例えば、人の乗り降りや、5分以内の荷物の積み下ろしのための停止は、駐車には当たらないが、停車には該当する事となる。 類語・対義語 駐車 |
| 停車違反 | 停車禁止の場所・時間帯に停車を行った場合、違反となる。 |
| ディスクブレーキ | 自動車のブレーキの一種。 車輪と一体で回転する鉄製のディスク(=円盤)を、両側からパッドで挟み付けて止めるという仕組み。構造上、放熱性があり汚れにくい。 制動力が安定している一方で、力そのものはドラムと比べ強くない分、主に前輪に用いられる。 類語・対義語 ドラムブレーキ |
| ディーゼリング | エンジンキーを切ってもエンジンが停止せずにかかりっぱなしになる状態。 ランオンともいう。 |
| ディーゼルエンジン | シリンダ内に空気だけを吸いこみ圧縮して高温(500~700℃)にし、そこへ燃料の軽油を噴射して、自然着火により爆発させ動力を発生させるエンジン。 |
| 定地走行燃費 | 「平坦な道路を一定の速度で走行したとき、ガソリン1Lでどこまで進めるか」という燃費の基準の一つ。速度は、日本では60㎞/hが基準。 |
| 適性検査 | 職業・学科などにおける特定の活動にどれほど適した素質をもっているかを判定するためのもの。 視力・色彩識別・聴力・学力・身体能力等、運転に関する状況や動作の速さ、正確さなどを自覚するための検査。 |
| 手信号 | 警察官や運転者などが道路(とくに交差点)において、交通整理または意思表示のために行う指示する行為または、その指し示す表示の事である。警察官や交通巡査員による手信号が信号機の信号と異なる場合、前者の指示に従う。 |
| デフロスター | 四輪車において、窓ガラスの曇りを除く装置。 エアコン内のシステムとして湿度の低い温風を吹き付けるほか、電熱線を使用したものもある。 |
| デュアルパーパス | 舗装路でも未舗装路でもある程度走れるように作られた、文字通り「二つの(=デュアル)用途(=パーパス)」を持つ自動二輪車の事。 |
| デリニエーター | 路端や道路線形を示すために配された丸い小さな反射板。 ドライバーの視線誘導の役目を果たす。 高速道路では、50メートル間隔についている。 |
| 転回 | Uターンやスイッチターンなど、車両等がその進行方向を逆にするため、進路を変えること。 |
| 点数制度 | 運転者の過去3年間の交通事故・違反に対して一定の点数をつけ、その合計点数がある基準に達した場合に、運転免許の取り消しや停止処分を行う制度。 |
| 点数切符 | 軽微な交通違反(シートベルト装着義務違反など)に対して交付される切符で、その色から「白切符」といわれる。反則金は発生しないが、違反点数が加算される。免許証のない自転車は発行の対象外となる。 類語・対義語 交通切符 |
と
| 登坂車線 | 上り勾配の道路において速度が著しく低下する車両(例えば重量の大きな車両や特殊車両など)を他の車両から分離して通行させる事を目的とする車線をいう。 |
|---|---|
| 道路 | 歩行者、自動車などが通行するために設けられた通路。 法律上は道路法上の道路と、建築基準法上の道路がある。 道路法の「道路」は公道であり、道路構造令による幅員・構造などの基準が定められている。 建築基準法上の「道路」は公道以外に位置指定道路なども含む。 それ以外のものは法律上は「道路」とは位置づけられず、「道」などと呼ばれる。 |
| 道路交通法 | 道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資する事を目的とする日本の法律である。 略して「道交法」ともいう。 |
| 道路標示 | 道路の交通に関しての規制や指示を路面や記号に表示したもの。ペイントや鋲で表される。 |
| 道路標識 | 道路の傍らに設置され、利用者に必要な情報を提供する表示板である。 交通事故を未然に防ぐための規制・危険箇所への警戒喚起、指示・案内による交通の円滑化などを目的に設置される。 類語・対義語 本標識 補助標識 |
| 特定中型自動車 | 中型自動車のうち、車両総重量が8t以上11t未満、最大積載量が5t以上6.5t未満または乗車定員が11人以上29人以下のものをさす。マイクロバスなどがこの分類にあたる。 8t限定中型免許を持っているとき、その限定解除をすることでこの車両を運転することが可能となる。 |
| 特定届出自動車教習所 | 人的基準・物的基準・運営的基準に適合するものに対し公安委員会より指定を受けた自動車教習所。 道路交通法第108条の2の定めにより大型免許、中型免許、普通免許、二輪免許、二種免許を取得する際に、応急救護処置・高速教習・危険予測等の義務づけされた講習を取得時講習というが、この取得時講習を特定届出自動車教習所が特定教習を行う事により、取得時講習を免除される教習所。 |
| 飛び込み | 指定自動車学校へ通学せず、試験場・免許センターで実施される技能試験等を直接受験する事を指す。 |
| ドライビングスクール | 自動車学校 |
| ドライブ・バイ・ワイヤ | 自動車において、人間による操作部分の動きを、電気信号に変換して操縦・制御する方式のことを指す。 アクセルやステアリングなどの動きに、「バイ・ワイヤ」とつけて呼ばれることも多い。 |
| トラクション | タイヤが地面を蹴って前に進もうとする力。地面との摩擦係数や荷重などによってその大きさが変わる。そのため、二輪では体重のかけ方などで大きさを変える技法もある。 |
| トラクションコントロールシステム | 自動車の発進時や加速時に、エンジンやブレーキを制御する装置。 滑りやすい道でタイヤが空回りしてスリップすることを防止する役割を持つ。 |
| ドラムブレーキ | 自動車のブレーキの一種。 車輪の内部に取り付けたドラム(=円筒)の内側に摩擦材(ライニング)をつけたブレーキシューが装着され、ブレーキを踏むとシューが外側に押し付けられた摩擦で車輪を止めるという仕組み。 低コストで制動力そのものが強い一方、放熱性に難があるため、主に後輪に用いられる。 類語・対義語 ディスクブレーキ |
| 取消処分 | 運転免許の今後における効力を失わせる処分。 交通違反や交通事故を起こしたとき、または自動車等を運転すると著しく道路交通の危険が生じる恐れがあるときに執行される。 |
| 取消処分者講習 | 運転免許の取り消し、拒否処分等を受けた方が、再度、運転免許を取得する際に必ず受講しなければならない講習。取消処分者講習を受講すると取消処分者講習終了証書(1年間有効)が交付される。 |
| 取消処分者講習終了証書 | 取消処分者講習を受講すると交付される。 1年間有効。 |
| トリップメーター | 走行距離を表すメーターで、カウンタ-をゼロにして自分の計りたい区間を計測できる。 |
| トルク | エンジンの回転による駆動力のこと。 |
| トレッド | ①右のタイヤの中心と左のそれとの間の距離。 ②タイヤが地面と接する部分と、それに刻まれた溝。溝の刻み方や、設置部分の材質であるゴムの質が走り方に大きく影響する。 |
| トレーラー | 牽引用自動車に引かれて、荷物や旅客を運搬する車。この場合、けん引する方をトラクターという。 |
| ドロップヘッドクーペ | カブリオ |
合宿免許の用語(な~の)
な
| 内輪差 | 4輪ないしそれ以上の車輪を持つ車両が、カーブを曲がる際に回転中心側の前輪と後輪が描く円弧の半径に生じる差のこと。 |
|---|---|
| 七点確認 | 大型二種の発進時などの基本的な安全確認方法のひとつ。 基本的なルームミラー・左ミラー・左後方目視・右ミラー・右後方目視の五点確認に、車内目視と車両の直前直下の確認を加えたもの。 車両の直前直下の確認は、左ミラーに併設されている専用ミラーで行える。 類語・対義語 五点確認 |
| ナンバー | 道路運送車両法により、陸運局の自動車登録原簿に登録された番号。国や地方政府が発行する「ナンバープレート」に記される。 |
に
| 握りごけ | バイクで急ブレーキをかけたとき、タイヤの回転が止まり転倒してしまう現象。 |
|---|---|
| 入校不可地域 | 合宿での入校を禁止している地域。 自動車学校と同じ県内やスクールバスの送迎範囲内が対象となる事が多い。 |
| ニーグリップ | オートバイに乗車する際の基本的な姿勢の一つで、ひざを中心とした内股全体で燃料タンクを挟む事で下半身を安定して保持する事である。 |
| 二段階右折 | 道路の交差点で右折する場合に、交差点の側端(交差点の輪郭)に沿って曲がる事を言う。 |
| 二段階制 | 自動車教習は、教習段階として2段階に分かれる。技能と学科の二つの科目にそれぞれ第一段階・第二段階があり、各科目の試験をクリアすることで次の段階に進む。 |
| 日常点検 | 自動車を安全に使用するため、状況に応じて適切な時期に行われる、自主的な点検のこと。自家用車などは努力義務だが、事業用自動車(自動二輪車と計自動車以外)・レンタカー・特殊な条件のある自家用車(条件には軽自動車が除かれることが多い)は運行する前に、毎日一度行わなければならない。 四輪車の場合、原則として ・運転席での点検(ブレーキ・エンジン・ウィンドウの装備) ・エンジンルームの点検(機械内の様々な液体の量、ファンベルトの張り) ・車の周りからの点検(ライト・タイヤ) が行われる。 類語・対義語 定期点検 |
| ニュートラル | 中立という意味。 AT車は「N」の位置で、MT車の場合はギヤをどこにもいれていない真ん中の位置。 エンジンの力がタイヤに伝わっていない状態。 |
ぬ
| 抜け | マフラーの排気ガスの排出効率の良さのこと。 マフラーは太くまっすぐな方が抜けが良く、抜けが良いほど最高出力が高くなる。 |
|---|
ね
| 熱線 | ガラスのくもり除去や防止のため、主に後ろガラスに使われている細いニクロム線。 電気が流れるとガラスが暖められ、くもりが取れる。 |
|---|---|
| 燃料消費率 | 1リッターの燃料でどれだけ走るかを表したもの。略して「燃費」。 測定方法は、以前は10・15モードやJC08モードが使われていたが、現在ではWLTCモードが主流である。 |
の
| ノック (ノッキング) |
エンジンがガタガタ鳴ること。ノッキングともいう。 燃料が異常燃焼を起こしていることが原因である。 |
|---|
合宿免許の用語(は~ほ)
は
| バイアスタイヤ | タイヤの内部にある繊維層が、回転する方向に対して斜めに並んでいるもの。従来のタイヤはこの構造が主流であった。 乗り心地に関してはラジアルタイヤよりこちらが優れている。 類語・対義語 ラジアルタイヤ |
|---|---|
| ハイオクタン価ガソリン | レギュラーガソリンより高いオクタン価を持つガソリン。略して「ハイオク」という。 オクタン価が高いと、ノッキングと呼ばれる障害を起こしにくくなる。 |
| 排気ブレーキ | 主に車両総重量3.5トン以上のトラック・バスに用いられる補助ブレーキの一種。主にゆるい下り坂で使われる。 排気管内に設けたバルブを閉じることで、エンジン内の排気圧力を高めて回転を妨げる、という仕組みである。 |
| バイク | 日本国内におけるバイクとは、「自動二輪車」の意として使用される事が多い。 本来「バイシクル」の略であり、「自動二輪車」ではなく「二輪車」全般を指す言葉である。 |
| バイパス | 市街地などの交通量の多さを緩和するため、市街地を迂回して設けられた道路。 |
| ハイビーム | 自動車のヘッドライトを、やや上向き(地面と水平)に当てること。約100m先まで照らせる。 ヘッドライトを地面と水平に当てることで遠くまでを見通せる。 法令上「走行用前照灯」というように、夜間走行中は原則この状態で走行し、対向車・先行者がいる状態にロービームへ切り替える。 類語・対義語 ロービーム |
| ハイドロプレーニング現象 | 水の溜まった路面などを走行中に、タイヤと路面の間に水が入り込み、車が水の上を滑るようになりハンドルやブレーキが利かなくなる現象。 |
| ハイブリッドカー | 「複合型自動車」という別名の通り、異なる2つ以上の動力源を持つ車両。 日本では、電気モーターとガソリンエンジンで動くハイブリッド電気自動車を指すことがほとんどである。 |
| 倍力装置 | 広い意味ではプレス機などに備えられた、小さな操作力で大きな力を得る為の装置のこと。 自動車における倍力装置には、ブレーキブースターやパワーステアリングなどがある。主な役割は、運転手の操作力を低減する為の補助を行うことで、「サーボ機構」と呼ばれる装置が多く使われる。 |
| パーキングエリア (PA) |
高速道路や有料道路などに約15kmおき(北海道は約25kmおき)に設けられる比較的小規模な休憩施設のこと。 |
| パーキングブレーキ | 自動車のブレーキ機構のひとつで、名前の通り主に駐車時に使うブレーキ。 多くの場合、車の後輪を固定させる機能がある。 運転席の横にあるので、サイドブレーキともいう。 |
| バケットシート | 一般的な自動車用座席に比べ、左右の「へり」を極端に高め、尻や肩が深く包む事で体の固定機能を高めた形状のシート。 |
| ハザードランプ | 「非常点滅表示灯」というように、周りのドライバーに危険があることを示す為に点滅する灯り。 故障で路上駐車をしたりけん引されたりするときといった非常事態のほか、駐停車をするときや前方の渋滞を知らせるときにも使われる。 また、地域や状況によっては、法令に定められた使用方法ではないが、交通上での感謝の意を示す時にも使われる。 |
| 波状路 | 自動車教習所などで自動二輪車教習や技能検定に使用される不等間隔に開いた路地のこと。 |
| バス | 大量の旅客輸送を目的とする自動車のこと。 道路運送法では、乗車定員11人以上の旅客運送用のものと規定されている。 |
| バースト | タイヤが破裂すること。 トレッド部やサイドウォール部が一気に破壊され、タイヤの機能が失われるため、深刻な事故を招く事が多い。 |
| 発炎筒 | 自動車等に装備され、鮮やかな赤い炎を上げる筒状の道具。 主に緊急時等に本線車道や路肩に停車した場合において、後続車に対し前方に危険・障害物がある事を知らせるために用いられる。 |
| バックファイア | ガソリンエンジンで、オーバーヒートなどにより吸気バルブから混合気を吸入する時に自然発火してしまい、キャブレター側に炎が逆流する現象。 |
| パッシング | 自動車が上向き前照灯を点滅させたり、下向き前照灯と連続して切り替えたりして合図をすること。 向車線では右折待ちなど原則・停止して行われるときは道を譲る合図に、単に通行中の場合は「自分が先に行くので譲れ」、同じ車線中では「追い越しの合図」など、さまざまな意味を持つ。 |
| ハードトップ | 自動車のボディスタイルの一つ。硬い材質でできた屋根を持ち、側面の柱がない(または見えなくなっている)形をしている。 |
| バードビュー | 日本語で「鳥瞰図」というように、上空から斜めに見下ろしたような形式のもの。 カーナビなどで用いられる。 |
| 幅寄せ | 路肩に車を駐停車させる際、車を壁や縁石の近くに寄せること。 |
| ハブ | 車輪(あるいは円盤状の部品)の中心部にあって、車輪の外周にあるリムから出た全てのスポークが一点に集中する部分。 |
| パワーウェイトレシオ | エンジン出力(馬力)あたりの車両重量(kg)のこと。この値が高いと加速がしやすくなる。 |
| パワー・ステアリング | 運転者の操舵(ハンドル操作)を補助する機構。略して「パワステ」という。 この機構により、運転者は軽い力で操舵する事ができる。 |
| バン | 荷物の運送に使われる自動車の一種。箱型のフォルムで、車体後部まで屋根がついている。 小型のものを「ライトバン」という。 類語・対義語 ワゴン |
| バンク | 二輪車がカーブを走行する際に、車体を傾けながら曲がる技術。 |
| パンク | 何らかの原因でタイヤの空気が漏れ、そのままの状態では走行できず、修理する必要がある状態のこと。 |
| 半クラッチ | クラッチを完全につないでいない状態のこと。略して「半クラ」ともいう。 車両の状態に応じて適切なアクセル操作と半クラッチ操作を行わないと、乗員に衝撃を感じさせたり、クラッチジャダーやエンストを起こす。 こうした操作を多用しすぎると、クラッチ板のダンパースプリングの破損やフライホイール固定ボルトの破断といった重大な事態を招く事にもなるため、MT車の運転者は必ず習得しなければならない技術のひとつである。 |
| ハンドブレーキ | パーキングブレーキ、サイドブレーキの別称。 |
| ハンドルの遊び | ハンドルにおいて、動かしても反応しない部分。 この部分がないと少し動かしただけでタイヤが曲がるのでハンドル操作が非常に難しくなる。 |
| ハンドルの復元力 | ハンドルを切った後、力を緩めるとハンドルが元に戻ろうとする力のこと。 |
| 反応時間 | 運転においては、運転者が危険状態を認知してからブレーキをかけ、それが効き始めるまでの時間を指す。この時間に車が走る距離が空走距離となる。 反応時間は、反射時間(危険状態を認知してからブレーキのために体が動くまで)・踏みかえ時間(体が動いてからブレーキの体制に移るまで)・踏み込み時間(ブレーキをかけてから、それがききはじめるまで) の三つからなる。 |
ひ
| 非公認校 | 公認校と違って、公安委員会の許可を取っていない教習所。 カリキュラムの規制がなく教習時限を自由に設定できる一方で、指導力の水準に規定がない。 そのため個人個人の苦手な項目だけを指導するなど教習に柔軟性がある、安い料金に設定することができるといったメリットと教習の質にばらつきがあるというデメリットがある。 類語・対義語 指定自動車教習所 |
|---|---|
| ビジネスバイク | 荷物の運搬に使われる、商業用のバイクのこと。 荷台があるほか、文字通り仕事に使えるような実用性を追求したスペックを持つ。 |
| 非常点滅表示灯 | ハザードランプ |
| 標示 | 道路標示 |
| 標識 | 道路標識 |
| ピラー | 英語で「柱」という意味の言葉で、自動車の窓ガラスと窓ガラスの間の金属部分(窓柱)を指す。 |
| ヒール・アンド・トー | マニュアル車のスポーツドライビングにおける運転テクニックの一つ。 ・角を曲がるときにフットブレーキをかけて減速し、十分減速した時にクラッチを切る ・右足のつま先でブレーキを踏みつつ、そのかかとでアクセルをかけると同時にシフトダウン ・左足でクラッチを戻す ・アクセルをかける という手順である。手順の2番目がその名前の由来である。 |
ふ
| フィンガーシフト | 大型車に使用されるトランスミッションの仕組み。 操縦席に小さなシフトレバーを設け、その位置を電気信号に置き換えて変速する。変速は空気圧を用いて行われる。 運転時の労力を減らすことが出来る。 |
|---|---|
| フェード現象 | 長い下り坂でブレーキが効きにくくなる現象。フットブレーキを使いすぎることでブレーキパッドが高温になりすぎて劣化してしまうことが原因である。 |
| 幅員 | 道路のはば。標識で「幅員減少」とあるときは、一つの車線の幅が減ることを指す。 |
| 二人乗り (自動二輪車) |
自動二輪車で、後部座席を使って二人乗りを行う際、コーナリングや加減速の面で運転特性に違いがみられる。 そのぶん運転技術の習熟が必要とされるので、免許を取得してから一定の期間が経たないと二人乗り運転ができない。道路により二人乗りに関する規制も異なる。 一般道…普通二輪または大型二輪の該当する免許を取得してから1年経過して可能 高速道路…20歳以上、かつ普通二輪または大型二輪の該当する免許を取得してから3年経過して可能 |
| 普通自動車 | 車両総重量3,500kg未満、最大積載量2,000kg未満、乗車定員10人以下の四輪車のこと。 |
| 普通自動二輪車 | 道路交通法における車両区分の一つ。 排気量が50cc超400cc以下の二輪の自動車(オートバイ)のこと。 |
| フットレスト | ドライバーの左足を休めるため、または、コーナリングで足を踏ん張るために付けられた固定したペダル状のもの。 |
| 不凍液 | エンジンの冷却水の凍結を防ぐために用いる液体。 アルコールまたはエチレン-グリコールなどを主成分とする氷点降下剤。 |
| 踏切 | 道路と線路が同じ地面の上で交差する場所。 |
| フリクション・ロス | 特にエンジンで、金属やオイルの摩擦抵抗により無駄に損失したエネルギーの事。 |
| ブレーキ | 自動車の減速、または停止を行う装置。日本語では「制動装置」という。 類語・対義語 アクセル |
| ブレーキ・ブースター | ブレーキ装置の一つ。倍力装置の一種で、小さな力で大きな制動力(車体を原則・停止させる力)を得る。現在、大型車両の大半で用いられている。 |
| フレーム | 自動車において、車体の骨組みとなる枠のこと。 |
| フロアシフト | シフトレバーがフロア(車室の床)に配置されていることを指す言葉。 フロアシフトは現在最も一般的なタイプで、軽自動車から高級セダンまで幅広く使われている。 ほとんどの車種で車体中心線近くに配置されるが、レーシングカーでは競技規定に合わせ、右ハンドルの場合でも右シフトとなっているものがある。 類語・対義語 インパネシフト コラムシフト |
へ
| ペーパードライバー | 運転免許を取得し、現に有効な免許を保有しているものの、普段運転する事がない者や、運転する機会が無い者のこと。 また、二輪車免許を取得してこのような状態にある者を「ペーパーライダー」という。 |
|---|---|
| ベイパーロック | 液体などの蒸発で生じた気泡によって、ブレーキ等の油圧系が機能しなくなること。ブレーキに関しては、ブレーキを使いすぎることで中の液が過熱することが原因である。 |
| ヘッドライト (ヘッドランプ) |
前照灯 |
| ヘルメット | 二輪車を運転する際には、工事用ではなく乗車用ヘルメットを付けなければならない。 種類としては、フルフェイス(顔全体をカバー)、ジェット(顔部分が開いている)、ハーフ(125cc以下しか使えない)などがある。 いずれにしても、JIS、またはPSCステッカーを付けたものでなければならない。 |
| ベルリーナ | サルーン |
ほ
| ホイール | 車輪のこと。元々はタイヤやチューブまで回転部分全てを指す言葉だが、狭い意味ではそれらの軟質な部分を含まない部分を指す。 |
|---|---|
| ホイールスピン | タイヤの摩擦力を自動車の駆動力が超えたときに発生するスピンのこと。 タイヤが空回りして、エンジンの出力が無駄になると同時に、自動車のコントロールが難しい状態になるため、危険な状態といえる。 ホイールスピンは急発進、急加速、濡れた路面で起こりやすい。 |
| ホイールベース | 自動車において、前輪の車軸と後輪の車軸との間の距離のこと。軸距ともいう。 この距離が大きいと小回りが利きづらく、内輪差も大きくなる。 |
| 方向指示器 | 右左折や進路変更の際に、その方向を周囲に示すための保安装置である。 方向を灯火の点滅で示す事から、日本では通常、ウインカーと呼ばれている。 |
| 保管場所 | 二輪車を除く自動車は、自動車の使用の本拠の位置から2㎞以内(直線距離)で、道路以外の場所に保管場所を確保されなければならない。 新規に該当する自動車を登録したり保管場所を変更したりする際には、届け出をして、その後さらに保管場所標章の交付を受けねばならない。 |
| 歩行者横断禁止 | 道路標識。 この標識がある場所では、道路を横断してはならない。 なお、横断歩道での横断のみ許可する場合には「横断歩道を除く」等の補助標識が付いている。 |
| 歩行者専用 | 道路標識。 歩行者による移動の安全性確保や、スポーツ、レクリエーションとして、道路の全部を歩行者だけで利用する事を目的とした道路である。 |
| 歩行者通行止め | 道路標識。 歩道がないなど、歩行者が通行しにくい道路に設置される。 |
| 補助ハンドル | 教習車の助手席などにに取り付けられているハンドル。 教習中、主に危険を回避する場合に教官が車を操作する為に使用する。 |
| 補助標識 | 規制の理由、規制区間の特定、規制が適用される日時、車両の種類の特定など、本標識を補足する標識で、通常、本標識の下に取り付けられる。 |
| 補助ブレーキ | 教習車の助手席などにに取り付けられているブレーキ。 教習中、主に危険を回避する場合に教官が車を停止する為に使用する。 |
| ボックス | 乗用車の形状でよく用いられる単語。エンジン・座席・トランクの部分が車体にどう収まっているかを表す 3ボックスカーはエンジンのあるボンネットとトランクスペースが突き出したもの、2ボックスカーはトランクスペースが座席と一体化したもの。1ボックスカーはエンジン・座席・トランクのスペースが一体化したものをさす。 |
| ボディー | 自動車では、文字通り車体を指す。そのデザインで車の印象も大きく変わる。 |
| 歩道 | 車道等に併設され、歩行者の通行のために構造的に区画された道路の部分をいう。 類語・対義語 車道 |
| ホーン | 警笛 |
| 本線車道 | 高速道路で通常走行する車線(本線車線)により構成する車道部分。 |
| 本標識 | 道路標識のうち、交通規制などメインの内容を示すもの。 特定の通行方法を禁止・指定する規制標識、交通上可能なことや決められた場所を示す指示標識、前もって注意すべき事項を知らせる警戒標識、地名や方向を示す案内標識の4つに分類される。 |
| ポンピングブレーキ | 自動車を減速させる際、フットブレーキを2~3回ほど踏んだり離したりを繰り返す運転技術。 主に後続車に減速を知らせる目的や、急ブレーキを防止目的で行う。ABS非装着車では、凍結路などでのタイヤのロックを防ぐ技術としても用いられた。 |
| 本免試験 | 教習所を卒業後、住所を管轄する運転免許センターで受ける試験。 この試験に合格すると運転免許取得となる。 |
合宿免許の用語(ま~も)
ま
| 巻き込み | 方向転換の際、内輪差や運転席からの死角によって二輪車や歩行者などと車体の横面でぶつかること。 |
|---|---|
| マニュアルトランスミッション | 自動車、オートバイ、鉄道車両などに採用されているトランスミッション(変速機)の一種である。 一般的には5ないし6段階の前進用ギアおよび1段階の後進用ギアで構成される。 日本国内の自動車販売台数におけるMT方式のシェアは数パーセントに過ぎないが、耐久性や強度が求められる大型車や作業用車両、趣味性が強いスポーツタイプ乗用車などを主として需要がある。 類語・対義語 オートマチックトランスミッション |
| マフラー | 排気に際して発生した音を減らす装置。 エンジンから排出されるガスは高音高圧であるため、そのまま大気中に放出すると急激に膨張して大きな音をならす。この騒音を減らす機能があるのがマフラーである。 |
み
| みきわめ | 教習において、教習効果の確認のこと。 検定の練習+検定にとおりそうかどうかのチェック。 |
|---|---|
| みきり発進 | 前方の信号が青に変わる前に自動車を発車させること。信号無視や安全確認義務違反で道路交通法に抵触し、重大な事故につながる。 |
| ミニカー | 道路交通法令において総排気量50cc以下又は定格出力0.6kW以下の原動機を有する普通自動車。 |
| ミニバイク | 車体や排気量の小さい自動二輪車。 小回りが利くほか、排気量によっては定期点検を受けなくても良いものもある。 |
| ミニバン | ワゴンの一種で、車内の高さや長さを大きくとった車種のこと。 特に規格や技術的な定義は存在しない。 |
む
| 無免許運転 | 免許が必要なものを免許を受けない状態、または失効・停止中の状態で運転・操作すること。 |
|---|
め
| 目の順応 | 暗いところから明るいところに出た後にまぶしさを感じなくなることを明順応、逆に明るいところから暗いところに入った後に暗さの中でも物が見えるようになることを暗順応という。 暗順応の方がより時間がかかるが、どの順応もも見えにくい時間が発生するので要注意である。 |
|---|---|
| 免許 | 運転においては自動車運転免許証(車の運転を許可した事を示す証明書)をさす。 |
| 免許合宿 | 運転免許証を合宿で取得すること。 |
| 免停 | 免許停止。 定められた一定期間(180日以内の範囲)だけ運転できないこと。 類語・対義語 仮停止 |
| 免取 | 免許取り消し。 この処分を受けると、欠格期間経過後に「取消処分者講習」を受講し、最初から運転免許を取り直す事になる。 |
も
| モータースクール | 自動車学校 |
|---|---|
| モノコックボディー | フレームとボディを一体に作った車体。車内が広くなる、車両が軽量化できる、剛性が大きくなるなどのメリットがある。 |
合宿免許の用語(や~よ)
や
| 焼き付き | エンジンをはじめとする金属同士の摩擦部分において、冷却不良や潤滑不良などが原因で過熱し、溶けて固着してしまうこと。 |
|---|
ゆ
| 優先道路 | 交差点などで、この道路が優先道路である事を示すもの。 優先道路は交差する道路よりも道幅が明らかに広い道路の他、道路標識(本標識)で示されものもあたる。一方、交差する道路の方には「徐行」や「一時停止」の規制標識と、「前方優先道路」の補助標識がついていたりする。 |
|---|---|
| 優良運転者 | 継続して免許を受けている期間が5年以上で、かつその間に無事故無違反及び無処分並びに重大違反唆し等及び道路外致死傷がない者のこと。ゴールド免許の対象になる運転者 |
よ
| 幼児等 | 幼児(6歳未満の者)及び児童(6歳以上12歳未満)のことを指す。 道路交通法14条で、保護者は交通頻繁な道路、踏切とその付近で遊ばせたり一人歩きをさせてはならないと規定している。 |
|---|---|
| 予熱栓 | グロープラグ |
合宿免許の用語(ら~ん)
ら
| ライダー | rider(馬を駆る人)から、バイク等の乗り手のことを指すようになった言葉。 |
|---|---|
| ライディングポジション | バイクの乗車姿勢のこと。「ライポジ」と略される。 正しい姿勢でバイクを運転すると、体力を温存しやすく、ハンドルを適切に操作しやすい。そのため、ライディングポジションはバイクの安全運転に大きく影響するといえる。 |
| ラウンドアバウト | 中央に円形の地帯を設けて、車がその周辺を一方通行で回ることで進行方向を変えるようにしたタイプの交差点。 日本の改正交通法では環状交差点と呼ばれ、時計回りである。 従来のロータリーとの違いは、道路の輪の中を通行する車両に優先権があることである。 |
| ラジアルタイヤ | タイヤの内部にある繊維層が、回転する方向に対して直角に並んでいるもの。高速走行に向いている。 類語・対義語 バイアスタイヤ |
| ラジエーター | 自動車エンジン用の放熱冷却装置。エンジンの前にあり、走行中風を受ける事で中の水が冷える仕組みになっている。 |
| ラップ | コースの1周・1往復。これに要する時間をラップタイムという。 |
| ランオン | ディーゼリング |
| ランドマーク | 一定の地域を移動中にまたそこに戻ってくるための目印とする地理学上の特徴物を指す。 カーナビゲーション用の地図、携帯電話による道案内用の地図などの電子地図において、著名な建物などを特に「ランドマーク」として扱い、地図画面上に実物を模したアイコンを表示したり、その建物に関する詳細情報を案内する事がある。 |
り
| リバースステア | 自動車が旋回するとき、ハンドルの切れ角が一定であるにもかかわらず、速度が遅いときは車の回転半径がだんだん大きくなり、速度を速くすると回転半径がだんだん小さくなる現象。 |
|---|---|
| リム | 車輪の外縁部にあって全体の形状を支えている硬質の円環。 自転車やオートバイの場合、内側はスポークでハブに固定され、外側はタイヤを挟んではずれないよう押さえている。 自動車や一部のロードバイクの車輪には、リムとスポークが融合した形状の物もある。 |
| リムジン | 運転席と客席の間に仕切りをつけた大型(前後に長い場合が多い)の高級乗用車のこと。多くの場合、プロドライバーが運転する。 |
| リムジンバス | 空港での送迎や観光に用いられる、内装が豪華なバス車両。 |
| リーンバーンエンジン | 燃費を良くするために、通常よりも少ないガソリンの量で燃焼させるシステムをもったエンジン。 |
る
| 累積点数 | 自動車免許の制度において、過去3年間の危険行為(違反・事故)に対してつける点数。 加算式であり、累積点数が一定の基準点数が超えた場合に行政処分となる。 違反行為につけられる基礎点数と、交通事故に付けられる付加点数に大別される。 |
|---|---|
| ルーフキャリア | 屋根に荷物を載せて運転できるための装備。四輪車の屋根などに外付けで取り付ける。 |
れ
| 冷却水 | 高熱を発する機械などを冷やすために用いる水。クーラントともいう。自動車では、主にエンジンを冷却するものを指す。 |
|---|---|
| レッドゾーン | エンジンの回転数が限界に近い領域。 |
| レブリミッター | エンジンの回転数が規定を超えないようにするための装置。 |
ろ
| 路肩 | 道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために、車道、歩道、自転車道または自転車歩行者道に接続して設けられる帯状の道路の部分。 自動車(二輪のものを除く)の通行は禁止されている。 |
|---|---|
| 路線バス | あらかじめ設定された経路を定期的に運行するバス。 |
| 路線バス等優先通行帯 | 路線バス等が道路の定められた部分を通行するようにするために、白線などの道路標示によって示されている部分。他の車両はこの通行帯を通行することもできるが、バス停から発進する路線バス等があるときは、路線バス等を優先させなければならない。 |
| 路側帯 | 歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分。歩行者(と一部の路側帯では軽車両)が通過できるが、車両は原則として通過できない。 |
| ロータリー | 交差点や駅前などにある、交通整理のため設けられた円形の地帯。車はこの円に沿って回る。 |
| ロービーム | 自動車のヘッドライトを、下向きに当てること。約40m先まで照らせる。法令上「すれ違い用前照灯」ともいわれるように、対向車や先行者の目をくらませたり雨や霧などの乱反射で自分の目がくらんだりする時だけ、ハイビームから切り替える。 類語・対義語 ハイビーム |
わ
| ワイパー | 窓ガラスの汚れや埃を拭き取る装置。 |
|---|---|
| ワイパーブレード | ワイパーのゴム以外の部分。 |
| 若葉マーク | 初心運転者標識 |
| ワゴン | 「ステーションワゴン」の略称で、長い箱のような車体をもつ乗用車の一種。後部座席は折りたたみ式になっており、荷物置き場にもできる。 荷物移動用のバンと似たフォルムをしているが、ワゴンは人間の移動がメインである。 類語・対義語 バン |
| わだち | 他の車が通り過ぎたときにできる車輪の跡。 雪道での安全運転には、この跡を利用することが重要である。 |
| 割り込み | 車両の運転においては、他の車両の進路上の前方に進路変更する行為を指す。 |
合宿免許の用語(英数字)
英字
| ABS | 「Anti-lock Brake System」という正式名称の通り、強くブレーキをかける際にロック(車輪の回転が止まる事)を防ぐ装置。 急ブレーキの際に車両の進行方向の安定性を保ったりハンドル操作で障害物を回避できる可能性を高めたりする役割がある。 仕組みとしては、タイヤの回転をセンサーで検出してモニターし、ロックを検知するとコンピュータに記憶している制御条件に応じて、ブレーキの液圧を調整し、停止させる力を最大に保っている。 |
|---|---|
| ACC | 「Adaptive Cruise Control」の略。 自動車で、コンピュータが先行車との車間距離を測り、自動的に速度や車間距離を保つ補助装置。 |
| AEB | 自動緊急ブレーキという別名のとおり、自動車において、障害物や人間を検知すると自動的にブレーキがかかるシステム。 レーダーやカメラなどで障害物を探知し、警告がかかるという仕組みである。 |
| AT | オートマチックトランスミッション |
| CVT | 無段変速機という正式名称の通り、ギアを用いず無段階で変速するための装置。特に小型自動車やATバイクなど、小排気量の車に多く採用される。 燃費を抑え、滑らかな速度調整が出来る一方、高速域での走行は得意でないという弱点もある。 |
| ESC | 「Electric Stability Contorol」の略で、急カーブなどのハンドル操作時や濡れた道路の走行などにおいて、自動車がスリップしそうになるのを防ぐ装置。 コンピュータが車両状態をチェックし、ブレーキなどに働きかけているという仕組みである。 |
| ETC | 「Electronic Toll Collection(電子料金収受システム)」という名称の通り、有料道路を利用する際に料金所で停止する事なく通過できるための、電子機器によるシステム。 |
| GPS | 「Global Positioning System(全地球測位システム)」の略で、米国によって運用される衛星測位システム(地球上の現在位置を測定するためのシステムの事)を指す。 |
| IC免許証 | ICチップ(半導体集積回路)を内蔵した運転免許証のこと。 本籍情報は、個人情報の保護のため表面に印字ではなくICチップに(日本国籍を有しない者はその国籍)記録されるようになった。 |
| JC08モード | 自動車使用環境をもとに走行パターンを仮定して割り出した、モード燃費の一つ。 実際の走行と同様に細かい速度変化で運転するとともに、エンジンが暖まった状態だけでなく、冷えた状態からスタートする測定が加わった。 |
| LKAS | 自動車で、カメラが車線を区切る白線を見分けることで、車線からの逸脱を防ぐように補助する仕組みのこと。 補助方法としては、ステアリング補助や警報などがある。 |
| LLC | 自動車の冷却水の中でも、氷点を下げる添加剤を含み、年間を通じて使用できるもののこと。 ロングライフクーラント(ずっと使える不凍液)の略。 |
| Nシステム | 道路を走行する車のナンバーを読み取り、記録する装置。 犯罪捜査等を目的に主要道路に設置されている。 |
| MT | マニュアルトランスミッション |
| OD式安全性テスト | 安全運転に必要な要素の備わり方を判断するためのテスト。16の特性から、運転適性度と安全運転度の総合評価からそれぞれを五段階に評価して、二つの評価の座標から運転適性を4つのタイプに分類する。 |
| RPM | 「Revolution Per Minute」の略で、クランクシャフトの1分間の回転数。 |
| RV | 「Recreational Vehicle」というように、野外のレクリエーションに使える多目的用途の自動車の略。 ワンボックス車やオフロード車、ステーションワゴンなどがこの種類にあたる。 |
| S字 | Sの字に曲がった形状を指すコース名。 |
| WLTC | 燃費の試験法の一つ。「Worldwide-harmonized Light vehicles Test Cycle(世界統一試験サイクル)」という正式名称の通り、国際的な方法となっている。 市街地モード(比較的低速な走行)、郊外モード(信号や渋滞などの影響をあまり受けない走行)、高速道路(高速走行)の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した形である。 |
数字
| 2WD | 自動車の駆動方法の一つ。2WDとは、ツー・ホイール・ドライブ(二輪駆動)の略である。 2WD車には、FR(エンジン前方・後輪駆動)やFF(エンジン前方・前輪駆動)などの種類がある。 |
|---|---|
| 4WS | 自動車のハンドルの仕組みの一つ。通常はハンドルを動かせば前輪だけが動くが、このシステムは後輪も同時に向きを変えられる。この事で、急角度なコーナーでの小回りや高速旋回時の走行安定性が良くなる。 4WSとは、フォー・ホイール・ステアリング(四輪操舵)の略である。 |
| 4WD | 自動車の駆動方法の一つ。4つある車輪すべてに駆動力を伝え、4輪すべてを駆動輪として用いる。この事で、悪路の走破力が高くなる。 4WDとは、フォー・ホイール・ドライブ(四輪駆動)の略である。 |
関連情報
合宿免許に役立つ情報