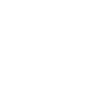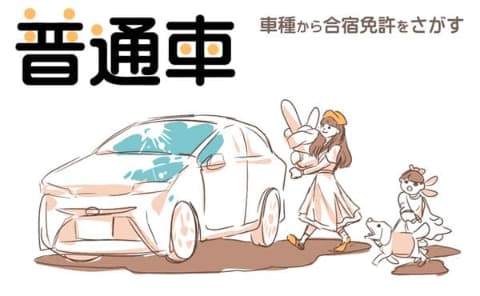- 免許の匠トップ
- 特定小型原動機付自転車とは?電動キックボードに免許がいるの?
特定小型原動機付自転車とは?電動キックボードに免許がいるの?
2024年7月以降、電動キックボードを初めにいくつかの乗り物が「特定小型原動機付自転車」と位置づけられ、従来とは違う交通ルールが適用されます。
ここでは、「特定小型原動機付自転車」の分類定義や、免許・運転に関するルールを紹介します。
特定小型原動機付自転車とは?電動キックボードは当てはまる?
2024年11月現在の道路交通法において原動機付自転車は、免許の必要な「一般原動機付自転車」と免許の不要な「特定小型原動機付自転車」に分かれています。
特定小型原動機付自転車は、下記の条件全てを満たしているものを指します。
| 車格 (車体のサイズ) |
長さ | 190cm以下 |
|---|---|---|
| 幅 | 60cm以下 | |
| 定格出力 | 0.60kw以下 | |
| 動力源 | 電気(外部電源) | |
| 最高速度 | 20㎞/h | |
| 走行中の設定変更は不可 | ||
| 変速機 | AT(オートマ) | |
| 最高速度表示灯 | 車体前部・後部に設置(緑色) | |
例えば、電動キックボードの多くやごく一部のモペット(フル電動自転車)が特定小型原動機付自転車にあたります。
逆に、このうち1つでも該当しないと、一般原動機付自転車とみなされ、免許が必要となり、適用される交通ルールも通常の原付と同じになります。一部の電動キックボードや多くのモペット等も一般原動機付自転車にあたります。車両の形状ではなく大きさやスペック・装備品によって判断される事に気を付けましょう。
特定小型原動機付自転車もあくまで原動機付自転車の一部なので、公道を走るには下記の条件も必要です。
- 装置などにおいて、道路運送車両法上の保安基準に適合している
- 自動車損害賠償責任保険(共済)の契約をしている
- 標識(ナンバープレート)の交付を受けている
保安基準の適合性については、地方運輸局による型式認定番号標、または性能等確認実施機関による性能等確認済みシールの有無が目安になります。
標識(ナンバープレート)は10cm四方のものを車体後部につける必要があります。
特例特定小型原動機付自転車とは?
特定小型原動機付自転車の中でも、下記の条件全てを満たしているものを「特例特定小型原動機付自転車」といいます。
- 走行中は最高速度表示灯が点滅する
- 最高速度表示灯が点滅する間に出せる最高速度が6km/h
- 側車を付けていない
- ブレーキが走行中容易に操作できる位置にある
- 鋭い突出部がない
特定小型原動機付自転車の中には、運転モードを切り替えることによって、通常の特定小型原動機付自転車から「特例特定小型原動機付自転車」に切り替えられるものもあります。
特例特定小型原動機付自転車とは、通常の特定小型原動機付自転車に対して、適用される交通ルールがやや異なります。詳しくは「交通ルール」の見出しをご覧ください。
運転するのに免許はいるの?年齢制限は?
「特定小型原動機付自転車」の条件に該当し、かつ公道を走れる条件があるなら、免許は要りません。逆に、「特定小型原動機付自転車」の条件に該当しない場合は、原付免許・小型限定普通二輪免許(またはその上位免許)・普通免許(またはその上位免許)のいずれかが必要となります。車両を入手したり運転したりする前に、該当するか確かめておきましょう。
しかし、年齢制限があり、16歳未満の人は運転を禁止され、罰則対象となります。16歳未満の人に提供(貸与・譲渡・購入)した人も同様に罰則対象となります。
交通ルール
特定小型原動機付自転車も道路交通法上は「原動機付自転車」という「車」にあたる為、様々なルールがあります。ここでは、特定小型原動機付自転車を運転するにあたってのルールを紹介します。
自転車や通常の原付と同様に、押して歩く場合は歩行者にあたります。
安全のため禁止されている事項
先述のように16歳未満の人が運転することは禁止されている特定小型原動機付自転車ですが、その他にも運転する上での禁止事項はあります。
飲酒運転
酒酔い運転・酒気帯び運転は禁止されています。お酒を飲んだら絶対に運転してはいけません。
また、上記に当てはまった場合、飲酒した人に車を提供した(車両提供罪)や飲酒した人の運転する車に乗った(同乗罪)・車に乗ってきた人に酒を出した(酒類提供罪)人も罪に問われますので注意しましょう。
ながら運転
スマホで話したり画面を操作したりしながらの運転は、罰則の対象(自動車・自転車と同様)となります。
また、イヤホンで動画や音楽を視聴しながらの運転も危険で、法令違反の可能性もあります。
二人乗り
通常の原付と同じく、二人乗りは禁止されています。
キックボードの場合、ボードの部分に子供1人くらいは載せられそうですが、それで運転することは法律上許されません。罰則の対象となります。
走るところ
歩道又は路側帯と車道の区別がある道路では、車道または自転車道を通らなければなりません。
車道を通る場合は、原則として道路の左端に寄って通ることになります。右側通行をしてはいけません。さらに、道路に車両通行帯がある場合は、原則として一番左側の車両通行帯を通ることになります。
これらに従わない場合は、罰則の対象となります。
特例特定小型原動機付自転車の場合
特例特定小型原動機付自転車は、歩道のうち「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識等が設置されてたものだけ通行できます。通るときも、中央から車道寄りの部分か普通自転車通行指定部分を通らなければなりません。
また、道路の左側に設けられた歩行者用以外の路側帯も通行できます。
これらの道を通る場合は、歩行者が優先となります。特に歩道を通る際、歩行者の通行を妨げることになる場合は一時停止しなければいけません。
これらのルールに反すると反則金対象となります。
横断歩道・交差点関連のルール
信号に従う事
信号無視の場合、通常の原付と同じく罰則の対象となります。
横断歩道は歩行者優先
横断歩道に近づいたときは、横断しようとする人が明らかにいない場合を除き、徐行して進まなければなりません。
歩行者が横断しているとき・横断しようとしている場合は、横断歩道の手前(停止線があるときは停止線の手前)で一時停止して歩行者に道を譲らなければなりません。
交差点における左折・右折の方法
左折の場合、事前に後方確認をしてウィンカーで左折の合図を行い、曲がるときはなるべく道路の左端に寄って十分速度を落として曲がります。その際は横断中の歩行者の通行を妨げてはいけません。
右折の場合は、二段階右折となります。原付と違って例外となる記載がないので、ほぼすべての交差点がそうなります。二段階右折に従わないと罰則の対象となります。
- 二段階右折とは
- 信号がある場合、青信号で交差点の向こう側まで直進し、停まって右に向きを変え、前方の信号が青になったら進みます。
- 信号がない場合、道路の左端に寄ってから交差点の向こう側まで直進し、十分に速度を落として右に曲がります。
これらに従わないと罰則の対象となります。
信号機がない交差点等を通る方法
交差する(横切って渡ろうとする)道路が優先道路である時・通る道路より明らかに広いときは、交差する道路の方が優先となります。横切る際はその道路を通る他の車両の進行を妨害しないようにすると同時に、徐行しなければなりません。
道路の優先関係がはっきりしない場合は左方優先になります。左側から交差点に進入する車両の進行を妨害してはなりません。
交差点内に入ろうとする時や通る時は、他の車両や歩行者のためなるべく安全な速度と方法で通らなければなりません。
これらのルールに反すると反則金対象となります。
標識・表示に従う事
特定小型原動機付自転車は、道路交通法上さまざまな標識・表示に従わなければなりません。ここでは、代表的なものを紹介します。
通行・侵入の禁止等
下記の標識がある所は通行・侵入してはいけません。反則金対象となります。
また、下記のような進行方向を指定する標識にも従わなければなりません。
一方通行には自転車・特定小型原動機付自転車のみ対象となる標識もあります(矢印の根元に自転車のピクトグラムがついています)。
一時停止
この標識がある時は、停止線の直前(停止線がない場合は交差点の直前)で一時停止しなければなりません。
軽車両対象の補助標識
道路標識の下に「自転車」「軽車両」と書いてある補助標識があったら、原則として特定小型原動機付自転車もその対象となります。
逆に「自転車を除く」「軽車両を除く」と書いてある補助標識があったら、原則として特定小型原動機付自転車もその対象でなくなります。
ただし、特定小型原動機付自転車だけを他の車両と区別する必要がある場合は、別に示されます。
その他交通ルール
駐停車について
普通車と同じ駐停車禁止場所・駐車禁止場所が適用されます。違反したら罰則が適用されます。
ヘルメットの着用(努力義務)
特定小型原動機付自転車を運転する際は、努力義務としてヘルメットの着用が課されています・
交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることが重要です。あくまで努力義務なので罰則等はありませんが、しっかり着用しましょう。
事故・違反があった場合
交通事故を起こした場合
交通事故を起こしたら、直ちに下記の行動を散らなければなりません。
- 危険防止措置:事故の続発を防ぐため、車両を安全な場所(路肩、空地など)に止める。構造上、エンジンを切る必要があるなら切る。
- 負傷者救護:負傷者がいる場合は医師や救急車を呼び、応急救護を行う(止血など)。危険防止措置上必要がある場合以外は、むやみに負傷者を動かさない(特に頭部を負傷した場合)。
- 警察官への報告:事故の場所、負傷者数や傷の程度、物の損壊の程度、事故車両の積載物などを警察官に報告し、指示を受ける。
これらの措置を講じなければ、「ひき逃げ」とされ罰則の対象となります。
特定小型原動機付自転車運転者講習
特定小型原動機付自転車の運転に関して一定の違反行為を繰り返した人は、都道府県公安委員会の命令で「特定小型原動機付自転車運転者講習」を受ける必要があります。
命令に従わなければ罰金対象となります。
まとめ
今回の記事の中で特に重要な部分を3つ選んでまとめました。
- 一定の条件を満たす電動キックボード等が「特定小型原動機付自転車」と認められている
- 「特定小型原動機付自転車」に認められた車の運転に免許は不要、しかし16歳以上という年齢制限あり
- 「車」の一種として様々な交通ルールに従わねばならない
また、車種分類方法については下記もご覧ください。
道路交通法上、電動アシスト自転車として判断されるには、運転者がペダルを漕ぐ力とモーターによる補助力の比が下記の基準をすべて満たす事が必要です。
・10km/h未満の速度では最大で1:2
・10km/h以上24km/h未満の速度の場合では走行速度が上がるほどアシスト比率が徐々に減少
・24km/h以上の速度ではアシストがない
そうでない場合、原付自転車と判断されます。
普通車の合宿免許・格安オススメ情報をチェック
合宿免許に関わるご相談を承ります